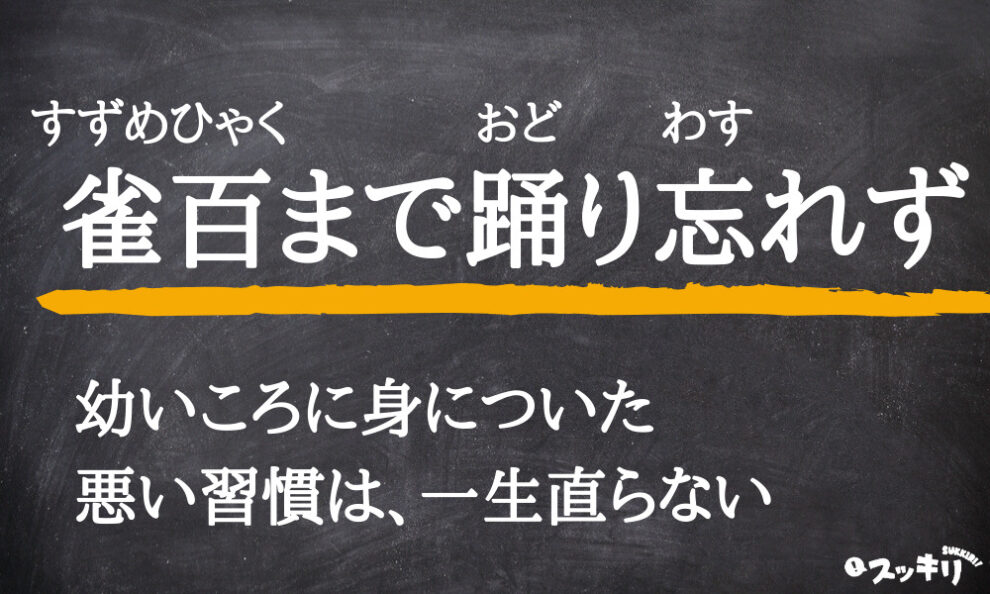「雀百まで踊り忘れず」とは「幼いころに身についた悪い習慣は、一生直らない」という意味です。
「雀が踊りを忘れない」ことが、なぜ「悪い習慣が直らない」という意味に繋がるのか、わからないという方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、「雀百まで踊り忘れず」の意味や使い方、由来などについて詳しく解説します。
☆「雀百まで踊り忘れず」をざっくり言うと……
| 読み方 | 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず) |
|---|---|
| 意味 | 幼いころに身についた悪い習慣は、一生直らない |
| 由来 | 上方いろはかるた |
| 類義語 | 産屋の風邪は一生つく 産屋の癖は八十までなおらぬ 三つ子の魂百まで など |
| 対義語 | 昔取った杵柄 |
| 英語訳 | What is learned in the cradle is carried to the tomb. (ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。) What is learned in the cradle is carried to the grave. (ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。) |
このページの目次
「雀百まで踊り忘れず」の意味
幼いころに身についた悪い習慣は、一生直らない
「雀百まで踊り忘れず」とは、「幼少期に身についた悪いくせは、歳を重ねても改善されない」という意味です。
このことわざに含まれる語を細かく分解すると、それぞれ以下のような意味を表しています。
- 雀
鳥のスズメ - 百まで
100歳まで - 踊り
リズミカルに飛び跳ねる - 忘れず
忘れない
上記をもとに考えると、「雀百まで踊り忘れず」は、「スズメは100歳まで、リズミカルに飛び跳ねることを忘れない」と言い換えることができます。
スズメは歩くときにヒョコヒョコと飛び跳ねますが、この習性は子どもの頃から死ぬまで変わりません。
そのため、「雀百まで踊り忘れず」は「幼いころの習慣は、年を取っても変わらない」という意味になっているのです。
なお、「雀百まで踊り忘れず」は悪い習慣のみに対して使い、良い習慣に対しては使いません。
「雀百まで踊り忘れず」にネガティブなニュアンスがあるのは、もともと「踊り」という語のメージから、以下のような “浮ついた人” に対して使われていたからです。
- 飲酒や博打(ばくち)などの習慣をやめられない人
- 浮気の癖がいつまでも抜けない人
なお、現在「雀百まで踊り忘れず」は、上記のような人だけでなく、悪い習慣が直らない人の全般に対して用います。
「雀百まで踊り忘れず」の使い方

「雀百まで踊り忘れず」は、主に以下のような言い回しで使います。
- 雀百まで踊り忘れずだ。
- 雀百まで踊り忘れずというから〜。
- 雀百まで踊り忘れずというのは本当で〜。
具体的な例文を見てみましょう。
- 私は猫背なのだが、幼少期の頃の写真を見たところ、背中を丸めている姿が写っていた。まさに雀百まで踊り忘れずだ。
- 雀百まで踊り忘れずというから、大人になってからマナーに困ることがないよう、幼い娘には正しい箸の持ち方をしっかり教えている。
- 雀百まで踊り忘れずというのは本当で、彼は物心ついたころから、やるべきことを後回しにしがちな性格だった。
すでに解説したとおり、「雀百まで踊り忘れず」は、「悪い癖が直らない」というネガティブな意味合いで使います。
そのため、「良い習慣がずっと続いている」という意味合いで使うことはできませんから、気をつけましょう。
× 彼は小さな頃から早寝早起きを欠かさない。まさに雀百まで踊り忘れずだ。
「雀百まで踊り忘れず」の由来
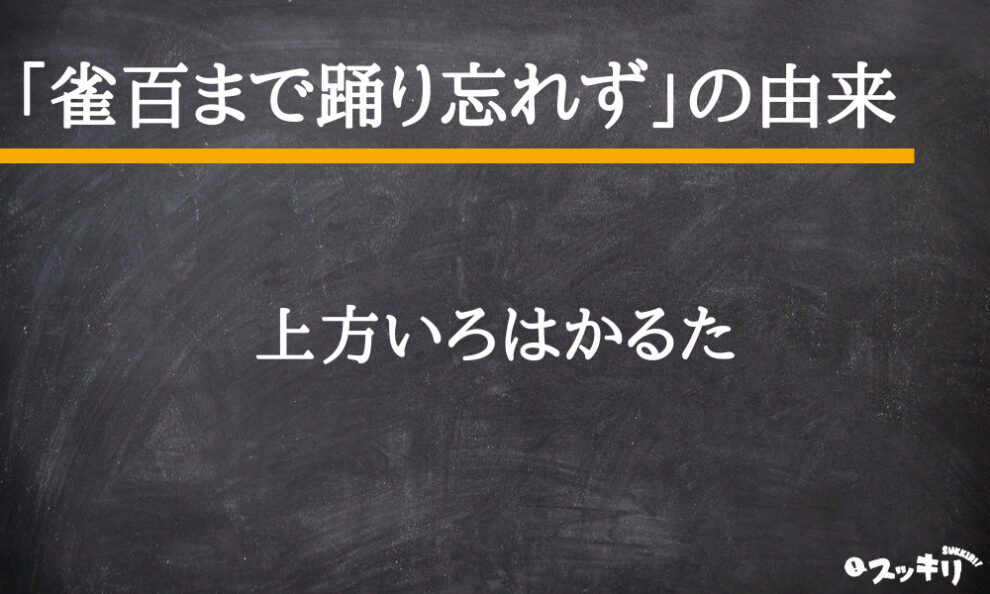
「雀百まで踊り忘れず」の由来は、「上方(かみがた)いろはかるた」にあります。
「いろはかるた」とはことわざが札に書かれている古典的なかるたですが、使われていることわざは、地域によって異なります。
「す」の札に「雀百まで踊り忘れず」が書かれているのが、関西の「上方いろはかるた」なのです。
なお、もともと「雀百まで踊り忘れ “ぬ” 」ということわざは存在していましたが、「上方いろはかるた」の表記がきっかけで、「雀百まで踊り忘れず」のほうが広く使われるようになりました。
「雀百まで踊り忘れず」は、『鷹筑波集(たかつくばしゅう)』にも編纂されています。
『鷹筑波集』は、1642年(寛永19年)に作られた俳句集です。
西武(さいむ)という人物によって編纂されました。
『鷹筑波集』には、300名以上の俳人の作品が掲載されています。
「雀百まで踊り忘れず」の類義語
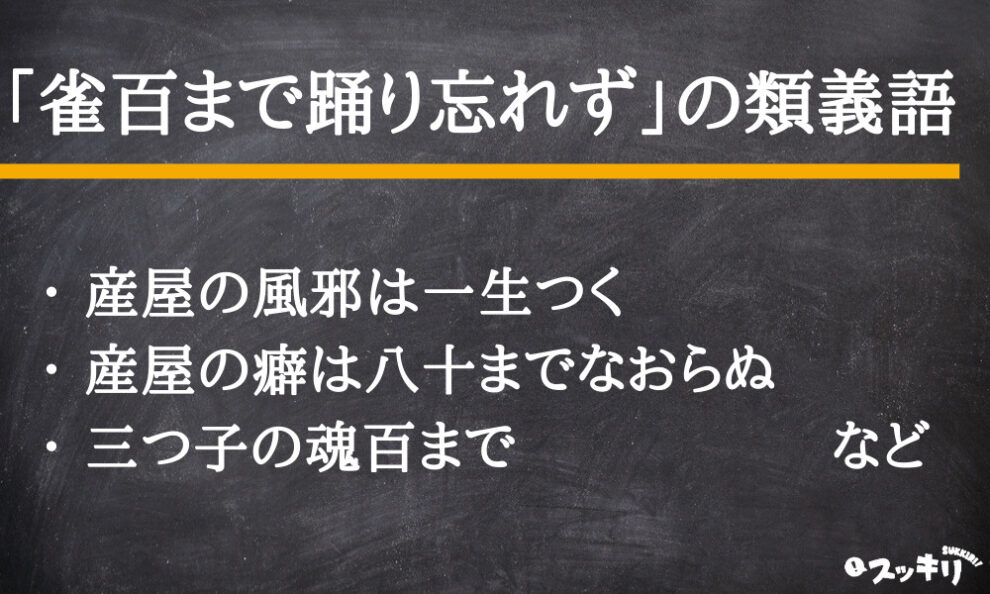
「雀百まで踊り忘れず」の類義語は、2つのパターンに分かれます。
- 悪い意味合いのみを表すもの
- 良い意味合い・悪い意味合いの両方を表すもの
以下、1つずつ解説します。
類義語①悪い意味合いのみを表すもの
以下の類義語は、悪い意味合いのみを表す言葉です。
- 産屋の風邪は一生つく
(うぶやのかぜはいっしょうつく)
幼いころに身についた癖は一生直らないということ - 産屋の癖は八十までなおらぬ
幼いころに身についた癖は年老いても直らないということ - 噛む馬はしまいまで噛む
悪い癖は死ぬまで直らないということ - 頭禿げても浮気はやまず
(あたまはげてもびょうきはやまず)
年をとっても浮気癖が直らないこと - 痩せは治るが人癖(ひとくせ)は治らぬ
痩せているのは治るが、悪い癖はなかなか改善されないということ - 病は治るが癖は治らぬ
病気は治るが、悪い癖はなかなか改善されないということ
上記の言葉は、「雀百まで踊り忘れず」と同じく、ネガティブな文脈のみで使います。
「産屋の風邪は一生つく」の意味を詳しく
「産屋の風邪は一生つく」とは、「幼いころに身についた癖は一生直らない」という意味です。
産屋とは、出産のために使う部屋のことです。
つまり、産屋は赤ちゃんが産まれる場所を指します。
そのため、「生まれた場所で引いた風邪が一生治らないこと」が、「幼いころの癖が直らないこと」」のたとえになっているのです。
「産屋の癖は八十までなおらぬ」の意味を詳しく
「産屋の癖は八十までなおらぬ」も、「産屋の風邪は一生つく」と同じく、「幼いころに身についた癖は一生直らない」という意味です。
「生まれた場所での癖は、80歳になっても直らないこと」が、「幼いころの癖が直らないこと」のたとえになっているのです。
「噛む馬はしまいまで噛む」の意味を詳しく
「噛む馬はしまいまで噛む」は、「悪い癖は死ぬまで直らない」という意味です。
人を噛んでしまう癖のある馬は、一生その癖が抜けません。
この道理が、「悪い癖が直らないこと」のたとえになっているのです。
「頭禿げても浮気はやまず」の意味を詳しく
「頭禿げても浮気はやまず」は、「年をとっても浮気癖が直らない」という意味です。
頭が禿げることが、年老いた状態のたとえになっています。
類義語②良い意味合い・悪い意味合いの両方を表すもの
以下の類義語は、良い意味合い・悪い意味合いの両方を表す言葉です。
- 三つ子の魂百まで
(みつごのたましいひゃくまで)
幼い頃の性格は、年をとっても変わらないこと - 漆剥げても生地は剥げぬ
(うるしはげてもきじははげぬ)
人や物の本質や性格は死ぬまで変わらないこと - 子供は大人の父親
大人の原型は幼少期につくられること
上記2つの言葉は、単に「昔から特徴が変わっていない」ことのみを表します。
そのため、ポジティブな文脈でも、ネガティブな文脈でも使うことができます。
しがたって、これらの言葉は、ネガティブな文脈で使う場合のみ、「雀百まで踊り忘れず」の類義語となるのです。
「雀百まで踊り忘れず」の対義語
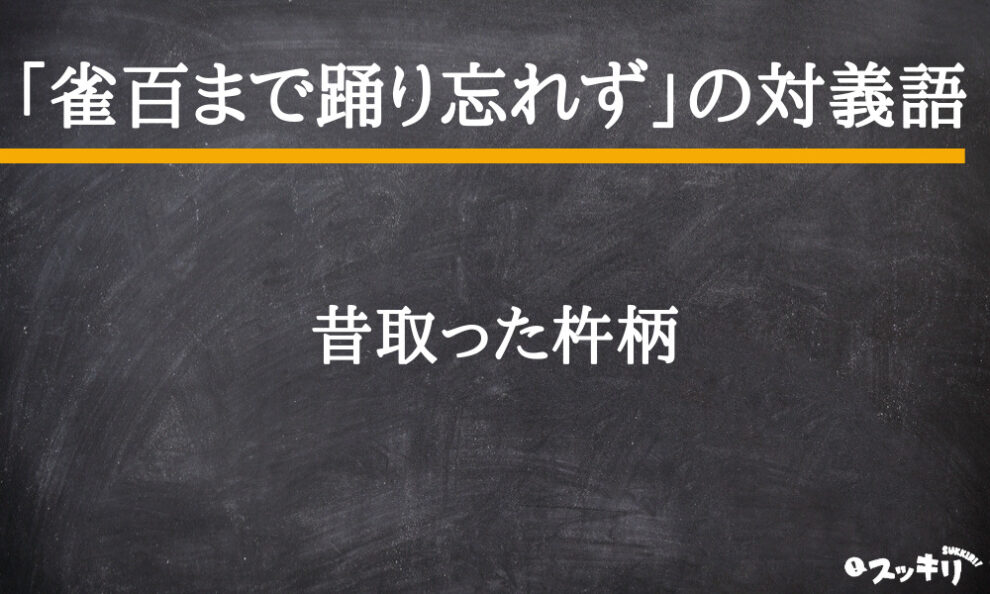
「雀百まで踊り忘れず」には以下のような対義語があります。
- 昔取った杵柄
(むかしとったきねづか)
①若い頃に身につけた能力
②若い頃に身につけた能力が衰えないこと
「昔取った杵柄」は、「若い頃の能力が、歳を重ねても保たれている」という意味であるため、“良い意味での変わらなさ” を表します。
そのため、“悪い意味の変わらなさ” を表す「雀百まで踊り忘れず」の対義語といえます。
「雀百まで踊り忘れず」の英語訳
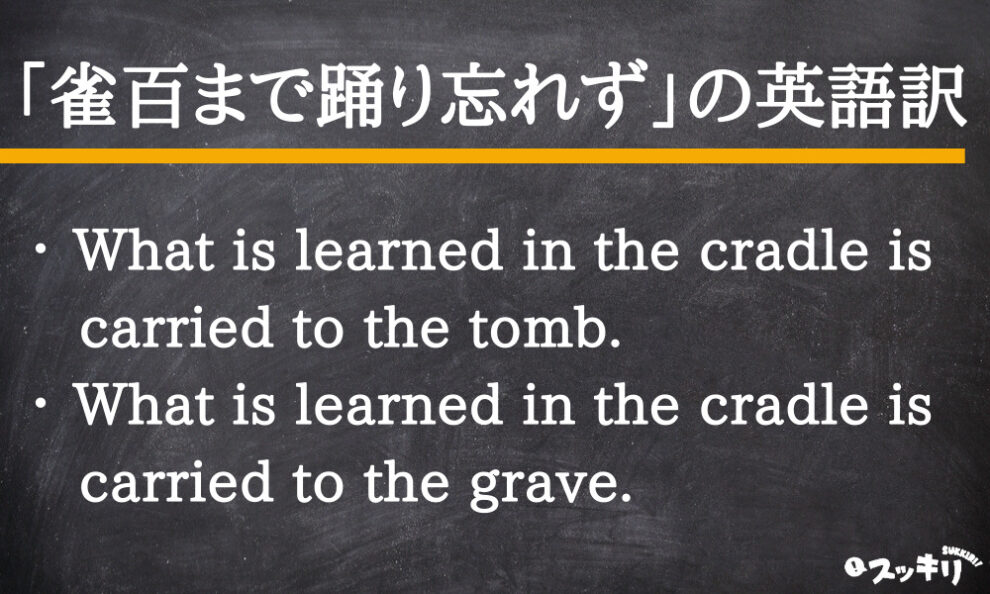
「雀百まで踊り忘れず」を英語に訳すと、次のような表現になります。
- What is learned in the cradle is carried to the tomb.
(ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。) - What is learned in the cradle is carried to the grave.
(ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。)
「雀百まで踊り忘れず」をそのまま英語に訳すと、“Sparrows do not forget dance until hundred.” となります。
しかし、この英語表現では、英語圏の人々に「幼いころの悪いくせは直らない」という意味は伝わらないため、注意しましょう。
補足:「雀」がつく言葉
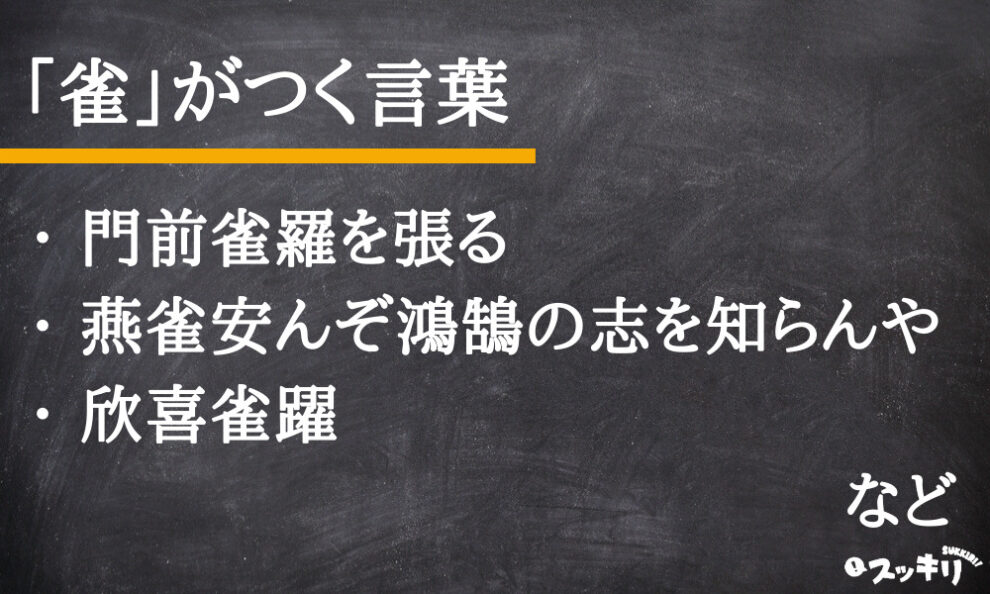
「雀百まで踊り忘れず」のほかにも、「雀」という言葉を用いたことわざや故事成語、四字熟語はたくさんあります。
参考までに覚えておきましょう。
- 門前雀羅を張る
(もんぜんじゃくらをはる)
訪れる人が誰もおらず、さびれていること
※雀羅:スズメを捕まえるための網 - 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや
(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや)
小物には大物の気持ちが分からないということ
※燕雀:小さな鳥 - 欣喜雀躍
(きんきじゃくやく)
踊り上がるほど非常に喜ぶこと - 雀の涙
(すずめのなみだ)
ごく僅かなもの - 雀の糠喜び
(すずめのぬかよろこび)
一時的に大喜びすること - 勧学院の雀は蒙求を囀る
(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)
見慣れたり聞き慣れたりしていることは、自然に身につく - 雀、海に入って蛤となる
(すずめ、うみにはいってはまぐりとなる)
思いがけない変化があること - 雀の千声鶴の一声
(すずめのせんこえつるのひとこえ)
つまらない者よりも、すぐれた者の一声のほうが勝っている
※「鶴の一声」ともいう
「雀百まで踊り忘れず」のまとめ
以上、この記事では「雀百まで踊り忘れず」について解説しました。
| 読み方 | 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず) |
|---|---|
| 意味 | 幼いころに身についた悪い習慣は、一生直らない |
| 由来 | 上方いろはかるた |
| 類義語 | 産屋の風邪は一生つく 産屋の癖は八十までなおらぬ 三つ子の魂百まで など |
| 対義語 | 昔取った杵柄 |
| 英語訳 | What is learned in the cradle is carried to the tomb. (ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。) What is learned in the cradle is carried to the grave. (ゆりかごの中で覚えたことは、墓場まで覚えている。) |
「雀百まで踊り忘れず」の意味からは、昔からの習慣を直すことはとても難しいことがわかります。
改善のためにできることを少しずつ始めたり、自分の良い部分を伸ばしたりしてみましょう。