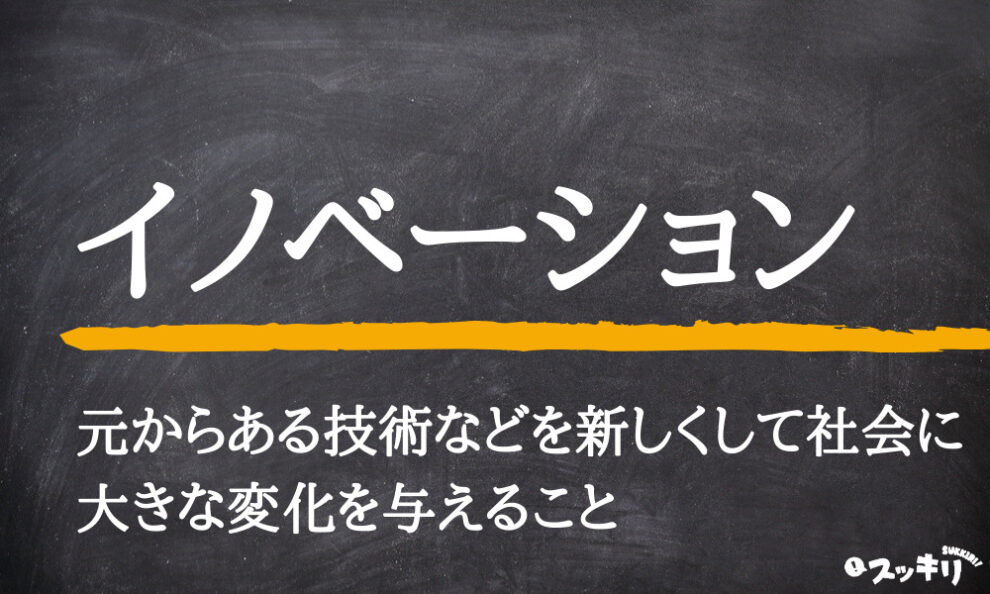イノベーションとは「元からある技術などを新しくして社会に大きな変化を与えること」という意味です。
イノベーションは、単に「技術革新」という意味の言葉だと思いますよね。
実は幅広い分野で使われる言葉なのです。
この記事では、イノベーションの意味や分類を詳しく解説します。
☆「イノベーション」をざっくり言うと……
| 英語表記 | イノベーション(innovation) |
|---|---|
| 意味 | 元からある技術などを新しくして社会に大きな変化を与えること |
| 語源 | 「何かを新しくする」という意味のラテン語 “innovare” |
| 類義語 | 革新 改革など |
| 対義語 | 保守 伝統など |
このページの目次
「イノベーション」の意味
元からある技術などを新しくして社会に大きな変化を与えること
例:イノベーションを起こすために行動する。
イノベーションとは、元からある技術などを新しくして社会に大きな変化を与えることを表す言葉です。
イノベーションは、「技術革新」という意味で使われることが多いです。
しかし、以下のように、技術だけではなく、経済活動における幅広い意味での革新を意味するのです。
- 新たな原材料の調達
- 新たな販売先の創出
- 新たな物流ルートの創出
変化の中でも「生産効率が上がる」「生産コストが下がる」などのよい影響を与える変化を表します。
基本的に、イノベーションが悪い方への変化を指すことはありません。
また、そのようなよい変化の中でも社会や業界全体にも影響を与えるくらいの大きな変化を指すのです。
「イノベーション」の分類
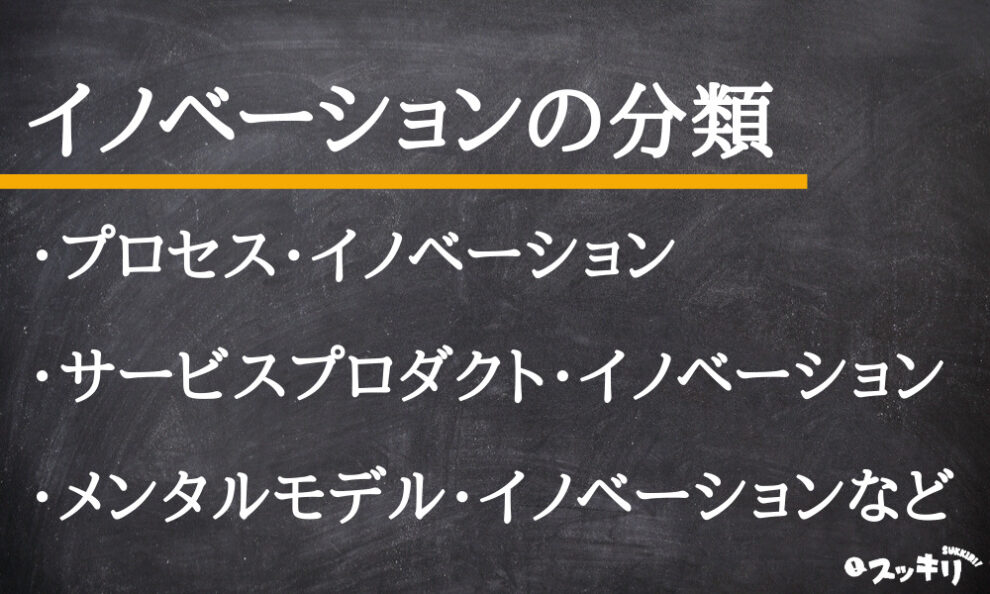
イノベーションは、以下のような視点ごとに5つに分類することができます。
- プロセス・イノベーション
- サービスプロダクト・イノベーション
- メンタルモデル・イノベーション
- サプライチェーン・イノベーション
- 持続的イノベーション
- 破壊的イノベーション
- オーガニゼーション・イノベーション
- マーケット・イノベーション
それぞれの種類の意味を詳しく解説します。
それぞれのイノベーションの種類ごとに、「ある企業の鞄」にイノベーションを起こすとしたらどのような方法になるのかという具体例を挙げます。
「プロセス・イノベーション」の意味
プロセス・イノベーションとは、生産方法や商品の提供の仕方を革新することです。
たとえば、鞄を生産している工場にロボットを導入して、生産性そのものを上げることがプロセス・イノベーションになります。
「サービスプロダクト・イノベーション」の意味
サービスプロダクト・イノベーションとは、商品自体の質を高めたり、全く新しい商品を発明したりすることです。
特に後者の意味で使われることが非常に多いです。
具体的には、新しいモデルの鞄を生産、販売することがこれに当たります。
「メンタルモデル・イノベーション」の意味
メンタルモデル・イノベーションとは、商品のイメージを変更することです。
広告やPRなどによって、商品に対する消費者の意識やイメージを革新することを表します。
たとえば、「その鞄をもっているとお金持ちに見える」というブランド性を持たせます。
「サプライチェーン・イノベーション」の意味
サプライチェーン・イノベーションとは、商品をつくるための材料や、その原材料の供給ルートを新たに開拓することです。
これによって、商品のコストを低下させたり、新しい素材を手に入れたりすることで、商品をよりよくできるのです。
「持続的イノベーション」の意味
持続的イノベーションとは、現在ある商品をより良いものにすることです。
たとえば、鞄のデザインを一新してより美しく、おしゃれなものにするのです。
「破壊的イノベーション」の意味
破壊的イノベーションとは、既存事業のルールを破壊し、業界構造を劇的に変化させるイノベーションのことです。
たとえば、タイプライターを使用していたところに、パソコンとプリンターが発明されることが破壊的イノベーションになります。
「オーガニゼーション・イノベーション」の意味
オーガニゼーション・イノベーションとは、組織変革によって業界や企業に大きな影響を与えることです。
企業が組織改革によって組織を健全化することによって、よりよい商品やサービスを生み出すことを表します。
「マーケット・イノベーション」の意味
マーケット・イノベーションとは、新たな市場に参入し、新たな顧客、ニーズを開拓することにより起こすイノベーションです。
それまで、鞄の購入者層としてターゲットにしていなかった層を新たに発見したり、開拓したりするのがマーケット・イノベーションです。
「イノベーション」の使い方
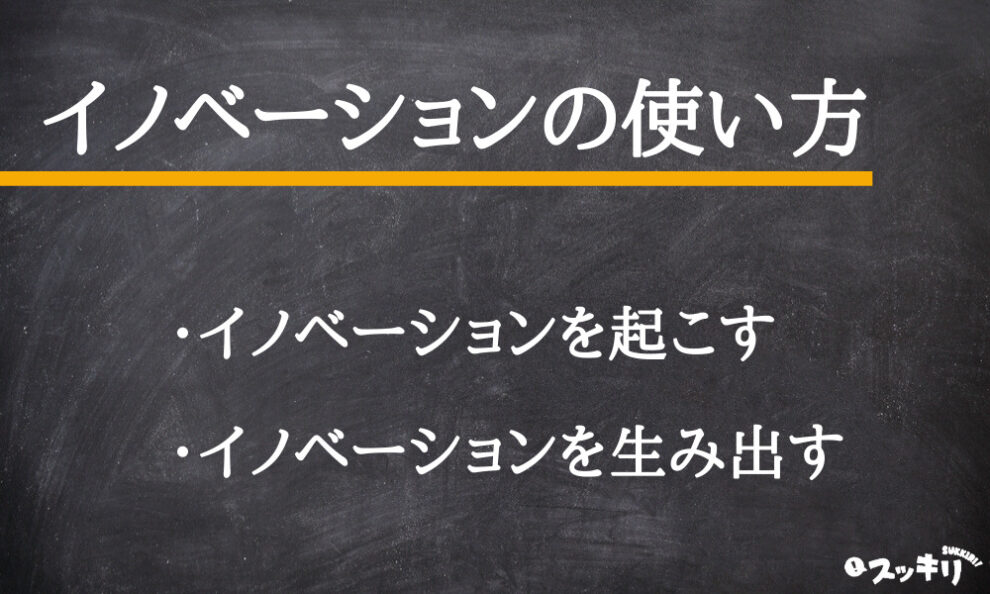
イノベーションは、以下のような形で使われることが多いです。
- イノベーションを起こす
- イノベーションを生み出す
実際の例文を見ていきましょう。
- イノベーションを起こすことで、一発逆転を狙う。
- この新商品は、我が社のイノベーションの結晶です。
- イノベーションを生み出すには、多大な努力が必要だ。
「イノベーション」の語源
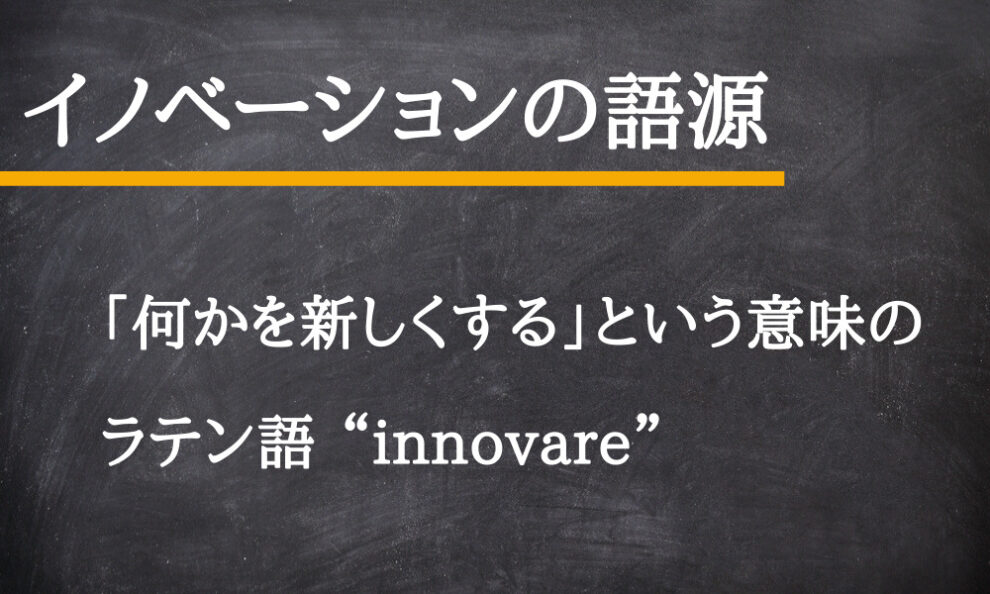
イノベーションの語源は、「何かを新しくする」という意味のラテン語 “innovare” です。
これが英語の “innovation” という単語に派生しました。
英語の “innovation” には、以下のような意味があります。
- 革新
- 技術革新
“innovation” をカタカナ語として表記したものがイノベーションです。
経済用語のイノベーションは、オーストリアの経済学者であるシュンペーターが提唱しました。
「イノベーション」の類義語
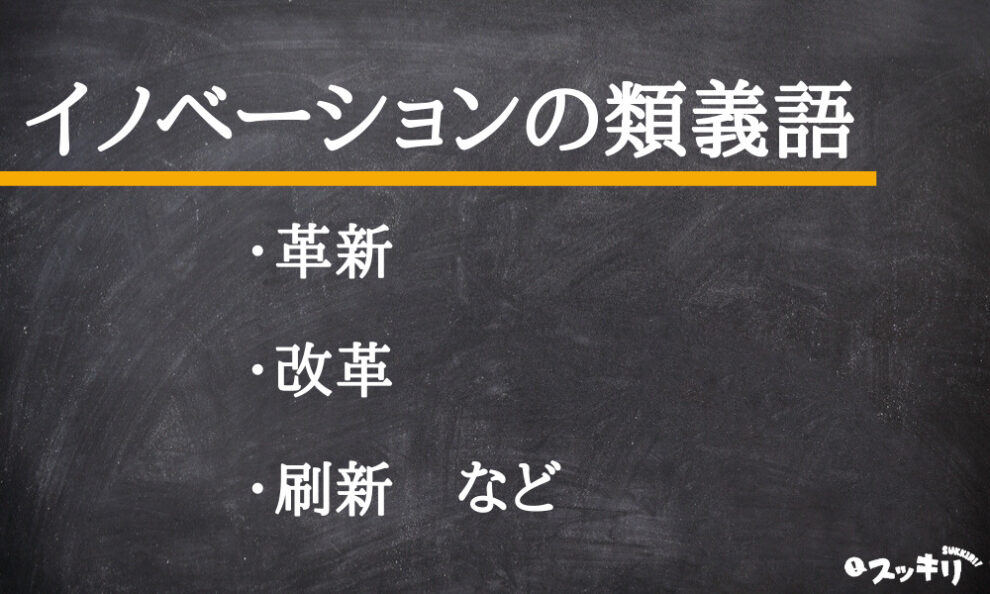
イノベーションには以下のような類義語があります。
「イノベーション」の対義語
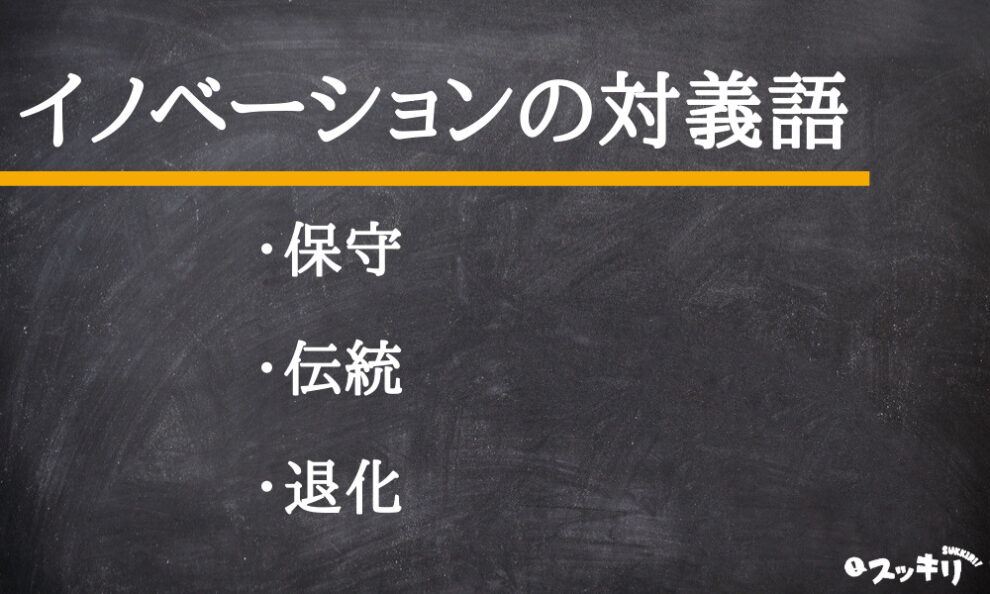
イノベーションには以下のような対義語があります。
- 保守
正常な状態を保つこと - 伝統
古くから受け継がれてきた事柄 - 退化
衰えたり規模が小さくなったりすること
「イノベーション」の関連語
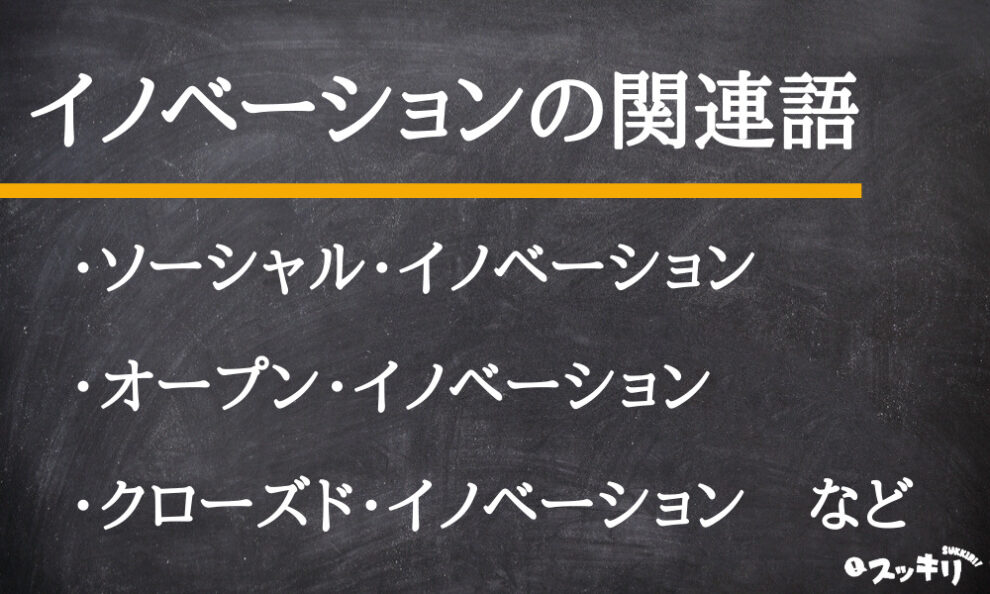
イノベーションには、以下のような関連語があります。
- ソーシャル・イノベーション
「社会の課題を解決する」という側面を重視したイノベーション - オープン・イノベーション
組織の枠組みを超えて、新たな技術や商品を開発すること - クローズド・イノベーション
研究開発などを全て一社の中で行い、情報も外に出さないようにするイノベーション - イノベーションのジレンマ
大企業が自社の技術に固執することで、新たな技術の登場に対応できず失敗すること - ライフイノベーション
医療・健康・福祉の分野で起こすイノベーション
「ソーシャル・イノベーション」の意味
「ソーシャル・イノベーション」とは、イノベーションの中でも特に「社会の課題を解決する」という側面を重視したイノベーションです。
具体的には、以下のようなものがソーシャル・イノベーションに含まれます。
- 政府の行う制度改革
- 企業やNPOなどによる事業
「オープン・イノベーション」の意味
オープン・イノベーションとは、「組織の枠組みを超えて、新たな技術や商品を開発すること」です。
以下のように業種や組織の構成などの枠を超えて行う商品開発や、技術開発のことです。
- 異業種交流プロジェクト
他分野の企業と協力して行うプロジェクト - 産官学連携プロジェクト
民間企業・政府・教育機関が既存の枠を超えて協力して行うプロジェクト
「クローズド・イノベーション」の意味
クローズド・イノベーションとは、研究開発などを全て一社の中で行い、情報も外に出さないようにするイノベーションの方法です。
しかし近年は、グローバル化や技術の拡大などによって一社のみがイノベーションを起こすことは難しくなってきています。
そのため、特に欧米の企業の間で、他企業や団体と協力するオープン・イノベーションが一般的になりつつあります。
「イノベーションのジレンマ」の意味
イノベーションのジレンマとは、「大企業が自社の技術に固執することで、新たな技術の登場に対応できず失敗すること」です。
大企業は優れた技術や競争力を持っていることが多いです。
しかし、その技術や過去のやり方に固執するあまり、新しい世の中の流れやイノベーションについていけなくなってしまうことがあるのです。
その現象がイノベーションのジレンマです。
「ライフイノベーション」の意味
ライフイノベーションは、医療・健康・福祉などの分野においてイノベーションを起こし、社会的に大きな変化を起こすことです。
特に、自国の革新的な医薬品や医療機器などの開発によって、健康寿命を延ばしたり、国際競争力を強化したりすることを表すこともあります。
「イノベーション」を起こせる企業
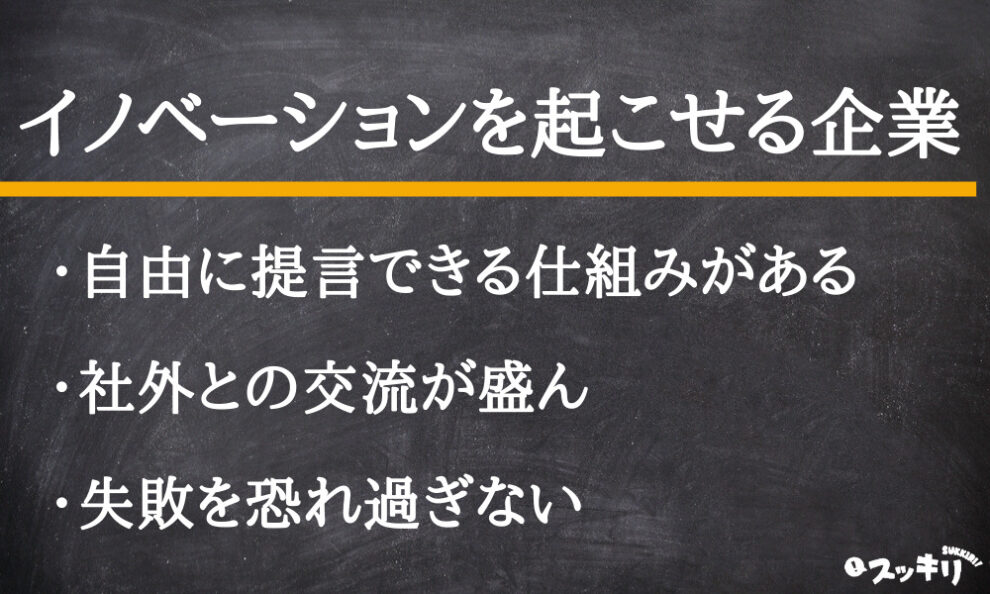
イノベーションを起こせる企業は、以下のような特徴を持っています。
- 自由に提言できる仕組み・風土がある
- 社外との交流・協業が盛ん
- 失敗を恐れ過ぎない
「イノベーション」を起こせない企業
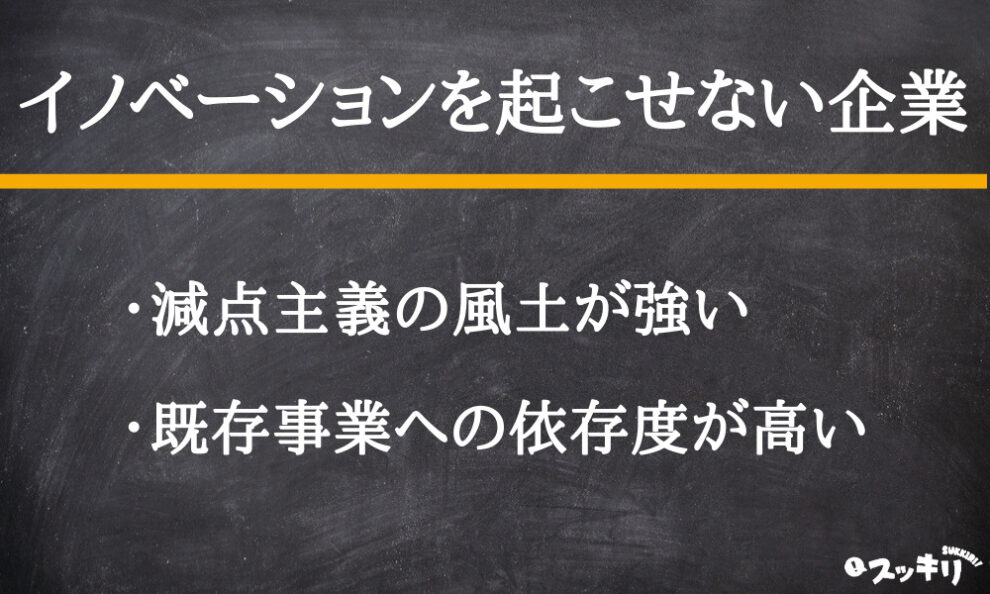
イノベーションを起こせない企業は、以下のような特徴を持っています。
- 減点主義の風土が強い
- 既存事業への依存度が高い
「イノベーション」の事例
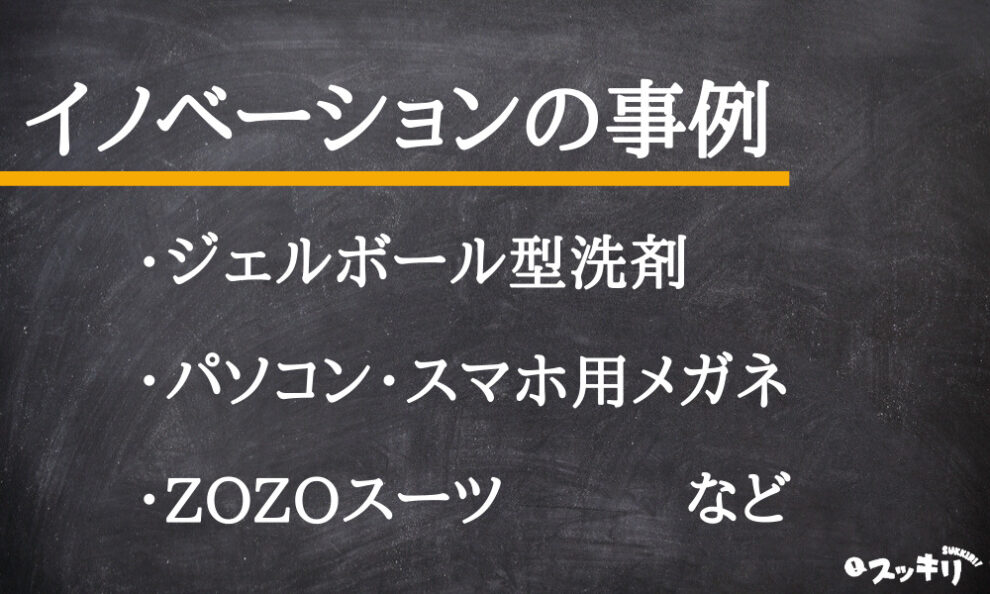
実際にあったイノベーションの事例を紹介します。
- ジェルボール型洗剤
- パソコン・スマホ用メガネ
- ZOZOスーツ
- トヨタ生産方式
それぞれの事例について詳しく解説します。
「ジェルボール型洗剤」のイノベーション
P&Gが発売しているジェルボール型洗剤は、1回分の容量が固形状になっている洗濯用洗剤です。
ジェルボール型洗剤は、それまで液体型や粉末型が主流だった洗剤にイノベーションを起こしました。
従来の洗剤に比べて「計量する手間が省ける」「計量や詰め替えの際に洗剤がこぼれる心配がない」などのメリットがあり、発売から3年で約1億個以上売り上げました。
ジェルボール型洗剤は、プロダクト・イノベーションによって生まれた商品だと言えます。
「パソコン・スマホ用メガネ」のイノベーション
パソコンやスマホ用のメガネは、電子機器から出るブルーライトをカットすることで、目への負担やダメージを減らすためのメガネです。
それまで、視力矯正器具としての役割しかなかったメガネに、全く新しい価値を付与しています。
パソコン・スマホ用メガネも、プロダクト・イノベーションのひとつです。
「ZOZOスーツ」のイノベーション
ZOZOスーツは、ZOZOTOWNが開発した、自宅で身体のサイズを自動計測できるボディスーツです。
伸縮センサーを内蔵した採寸ボディスーツであるため、一人で計測することができます。
ZOZOTOWNは、インターネット上の大手アパレルショップですが、オンラインショップでは試着ができないため、サイズ違いが大きな問題になっていました。
ZOZOスーツの開発によって、インターネット上での洋服の購入をより安易にしたのです。
ZOZOスーツは、プロセス・イノベーションのひとつです。
「トヨタ生産方式」のイノベーション
トヨタ生産方式とは、後の工程の作業員が必要な部品を、必要なときに、必要な量だけを前工程へと取りに行く生産方式のことです。
「かんばん方式」や「スーパーマーケット方式」とも呼ばれる方式で、部品の造りすぎを防ぐことができます。
トヨタ生産方式も、プロセス・イノベーションのひとつです。
「イノベーション」のまとめ
以上、この記事ではイノベーションについて解説しました。
| 英語表記 | イノベーション(innovation) |
|---|---|
| 意味 | 元からある技術などを新しくして社会に大きな変化を与えること |
| 語源 | 「何かを新しくする」という意味のラテン語 “innovare” |
| 類義語 | 革新 改革など |
| 対義語 | 保守 伝統など |
イノベーションには、さまざまな種類があることがわかりましたね。