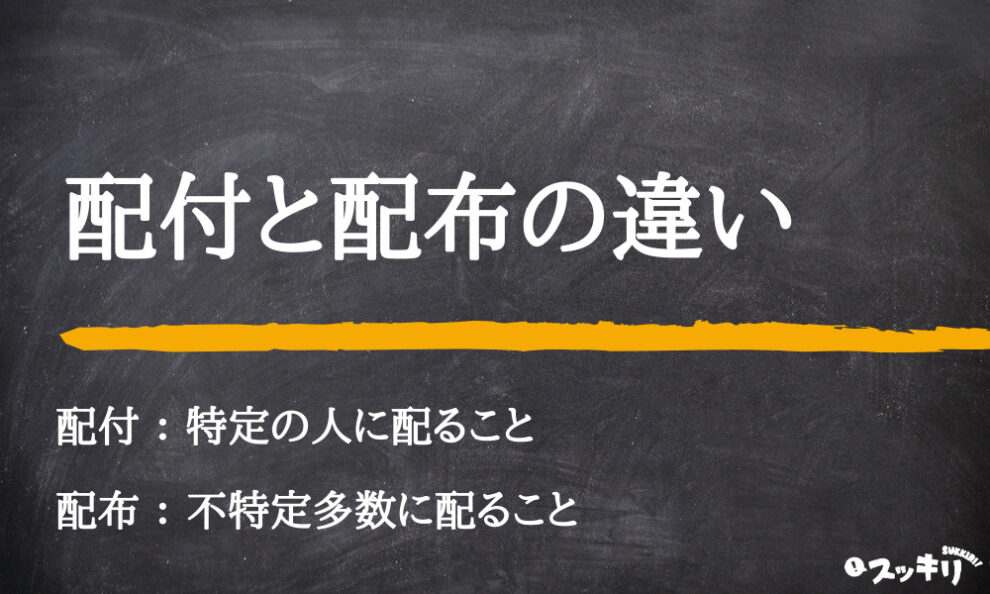配付は「特定の人に配ること」、配布は「不特定多数に配ること」を表します。
配布と配付は同じような意味であるため、どちらを使ったら良いか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では配布と配付の違いについて詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
「配付」と「配布」の違い
特定の人に配ること
例:受験生に解答用紙を配付する。
不特定多数に配ること
例:駅前でティッシュを配布する。
配付と配布では、「誰に配るか」が明確に異なります。
配付はひとりひとりに配り、誰に配ったか把握しています。
一方、配布の場合には、誰に配ったのか明らかではありません。
配付と配布の使い分けは、配付の漢字で覚えるのがおすすめです。
配付は「誰かに何かを付属させる」から「特定の人に配ること」の意味なのだと覚えると良いでしょう。
「配付」の意味
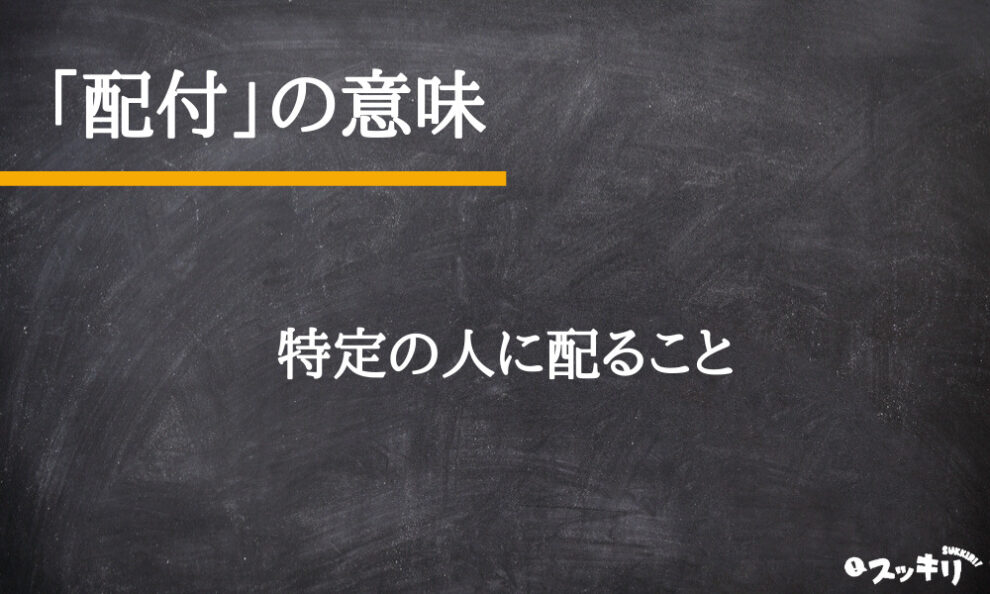
配付は「特定の人に配ること」という意味です。
「〇〇に✕✕を配る」という形で、配る対象が明らかになっていることが多いです。
そして、配る対象にもれなく何かを与える様子を表します。
たとえば、以下のような例文を考えてみましょう。
ワークショップの参加者にチラシを配付する。
この場合、ワークショップに参加した人全員にチラシが配られ、ワークショップに参加していない人には配られません。
このように、配付は配るべき人と配らない人が明確に区別されている時に用います。
配付は公文書や新聞などでは基本的に用いることができません。
公文書や新聞では「配布」表記に統一されています。
ただ、例外もあり、「贈与税配布金特別会計」など熟語の中では用いられる場合があります。
「配付」の使い方
配付は特定のグループに何かを配る時に使います。
具体的な例文を見ていきましょう。
- 従業員に給与明細を配付する。
- 全国民にマスクを配付する。
- 配付した資料は社外秘になっていますのでご注意ください。
❶、❷の例文のように、配付では「〇〇に」という形で誰に配るか示されてることが多いです。
一方、❸の例文のように誰に配るか直接は示されていない場合もあります。
ただ、直接示されていない場合でも、❸の例文では社員に資料を配っていると推測できます。
「配付」の漢字
配付の漢字を分解すると以下のようになります。
- 配
くばる - 付
手渡す
配付は「付」の「手渡す」という意味から、特定の人に一人ひとり渡すイメージになるのです。
「配布」の意味
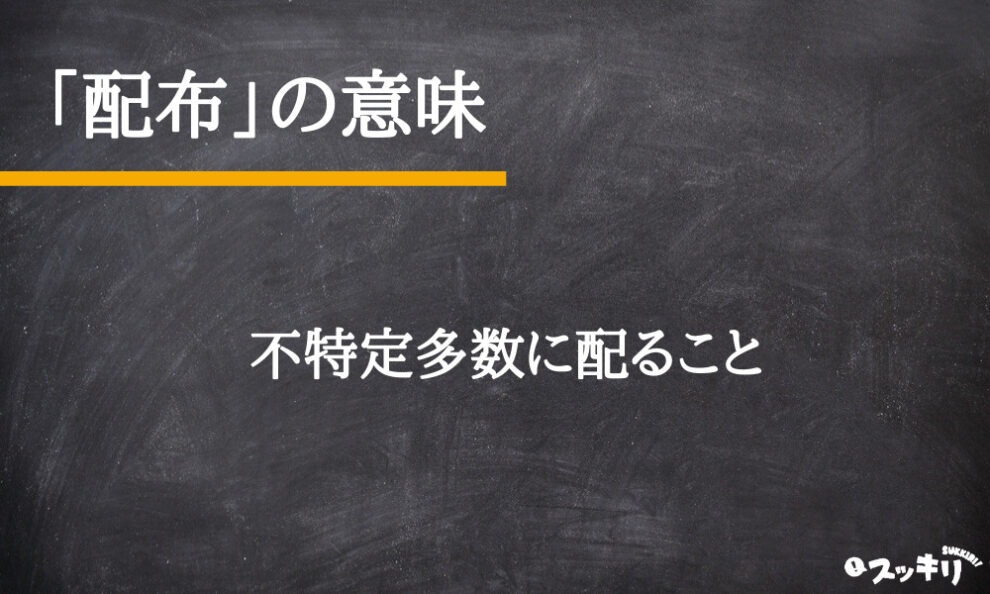
配布は「不特定多数に配ること」という意味です。
配布の場合には、配る対象は決まっていないことが多いです。
また、「〇〇に配布する」という形になっていても、〇〇に当てはまる人全員に配るわけではありません。
たとえば、以下のような例文で考えてみましょう。
駅前で女性にビラを配布する。
この場合、配る対象は女性に限定されています。
しかし、ビラを配る時に、駅にいる女性の全員に配ることはできませんよね。
このように、配る対象が決まっていなかったり、配る対象がいても全員にもれなく配らない場合には配布が用いられます。
上記のような使い分けとは関係なく、公文書や新聞などでは配布で統一されています。
一部の例外を除いて、配付が用いられることはありません。
「配布」の使い方
配布は不特定多数に何かを配る時に使います。
具体的な例文を見ていきましょう。
- 宣伝用のチラシを配布する。
- 試食用サンプルを配布する。
- ビラを配布するバイトを始める。
上記の例文のように、配布では誰に配るか示されていない場合が多いです。
「配布」の漢字
配布を構成する漢字には以下のような意味があります。
- 配
くばる - 布
広く行き渡らせる
配布は布の「広く行き渡らせる」という意味から、対象を限定せず不特定多数に配るという意味になったのです。
これで完璧!「配付」と「配布」の使い分けクイズ
配付と配布の使い分けクイズで、配付と配布を身につけられたか確認しましょう。
Q. デパートで無料サンプルをはいふする。
▼クリックして答えを見る
A. 配布
今回の場合、配る相手は不特定多数です。
デパートに来た人に配ることとになりますが、全員に配るわけではなく、デパートに来た人のうち、特定の誰か全員に配るわけでもありません。
そのため、配布が正解になります。
Q. 参加者に資料をはいふする。
▼クリックして答えを見る
A. 配付
今回の場合、参加者全員にもれなく資料を配ることになります。
そのため、配付が正解になります。
Q. 渋谷で20代の女性に化粧品サンプルをはいふする。
▼クリックして答えを見る
A. 配布
今回の場合、対象は「渋谷にいる20代の女性」ではありますが、全員に配るわけではありません。
そのため、配布が正解になります。
「配付」と「配布」の英語訳
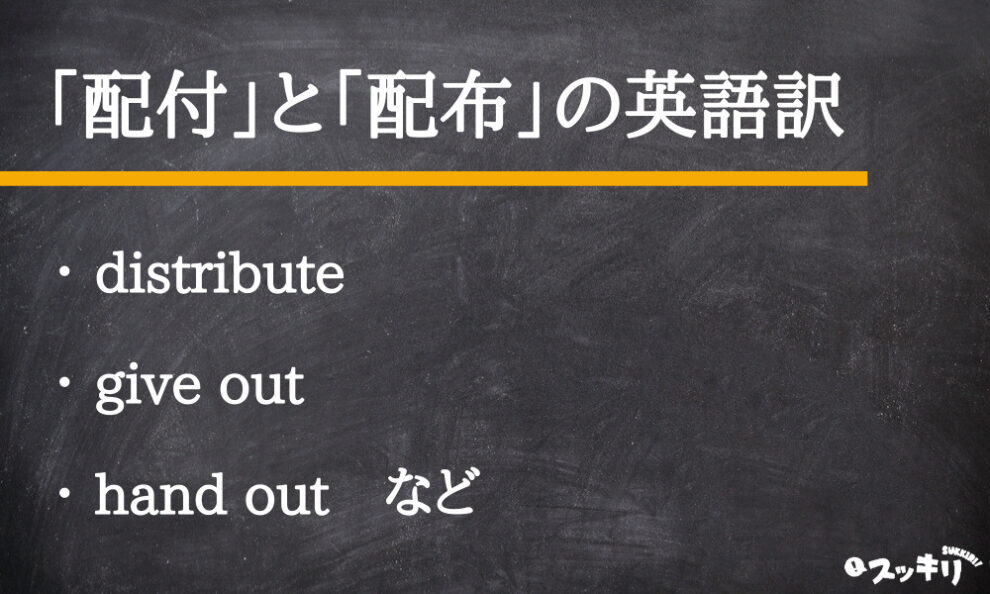
配付や配布を英語に訳すと以下のような表現になります。
- distribute
(配る)
例:Distribute goggles during a factory tour.
(工場見学でゴーグルを配付する。) - give out
(配る)
例:We will give out to leaflets.
(ビラを配布していく。) - hand out
(配る)
例:Hand these pamphlets out to visitors.
(来た人にパンフレットを配ってください。)
英語では、配付と配布が区別されないので、まったく同じ英語訳になります。
その他の配る表現
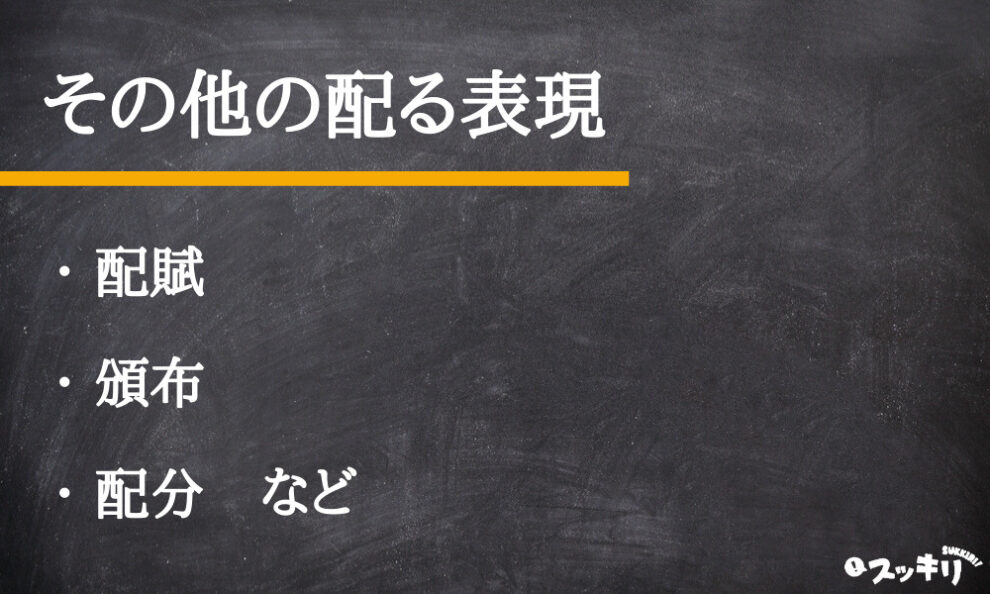
配付や配布以外にも、配ることを表す熟語は以下のようにいくつか存在します。
- 配賦(はいふ)
ひとりひとりに細かく割り当てること - 頒布(はんぷ)
不特定多数に配ること - 配分(はいぶん)
分け前を分け与えること - 分配(ぶんぱい)
多くの人に分け与えること
それぞれの言葉について詳しく見ていきましょう。
「配賦」の意味:ひとりひとりに細かく割り当てること
配賦(はいふ)は「ひとりひとりに細かく割り当てること」という意味です。
配布や配付と漢字は同じですが、お金が関わる場面で用いられることが多いです。
- 費用を各部門に配賦する。
「頒布」の意味:不特定多数に配ること
頒布(はんぷ)は不特定多数に配ることです。
配布とほぼ同じ意味ですが、配布では配った人に金銭を要求することはありません。
一方、頒布では無料で配ることもあれば、有料で配ることもあります。
- ライブ参加者限定グッズが頒布されていたので、つい買ってしまった。
「配分」の意味:分け前を分け与えること
配分は「分け前を分け与えること」という意味です。
あるひとかたまりのものがあり、それをどのような割合で分けるかが重視される言葉です。
- 利益を等しく配分する。
「分配」の意味:多くの人に分け与えること
分配は「多くの人に分け与えること」という意味です。
配分と似ていますが、分配は配ることを重視した表現になっています。
- 利益をスタッフ全員に分配する。
紛らわしい同じ読み方の熟語
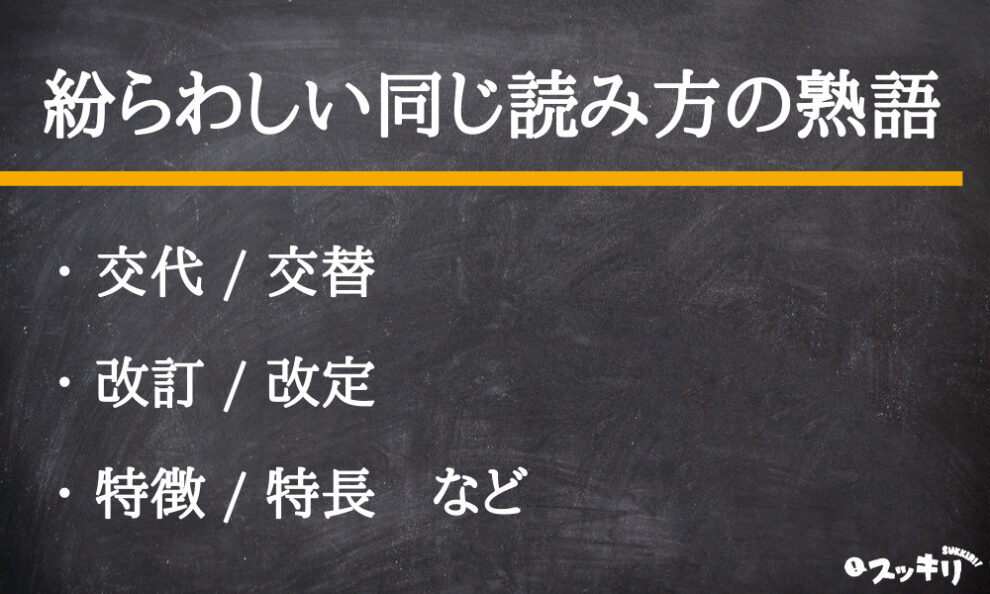
「配付 / 配布」の他に、意味が似ている同じ読み方の熟語には以下のようなものがあります。
- 交代 / 交替
- 改訂 / 改定
- 特徴 / 特長
- 追求 / 追及 / 追究
- 不審 / 不信
それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
交代 / 交替
交代と交替では、かわった後に後戻りができるかが異なります。
具体的には、以下のように異なります。
- 交代
役目などがかわり、後戻りはできない。
例:5点取られたピッチャーが交代する。 - 交替
役目などが繰り返しかわっていき、後戻りできる。
例:8時間経ったので見張りを交替する。
基本的には、一度かわった人が同じ役割に戻ってこれるかで判断すると良いでしょう。
改訂 / 改定
改訂と改定では新しくするものが異なります。
具体的には、以下のような違いがあります。
- 改訂
文章や書物の誤りを正すこと
例:教科書の改訂版を購入する。 - 改定
それまであった決まりを新しくすること
例:ルールブックを改定する。
それまでの内容が誤りだった場合には改訂を、誤りではないものの変えた場合には改定を用いると良いでしょう。
特徴 / 特長
特徴と特長では悪い意味でも使うかが異なります。
具体的な違いは以下のとおりです。
- 特徴
他のものと異なっていて目立つ部分
例:うさぎの特徴は耳が長いことだ。 - 特長
他のものよりも優れている部分
例:このエアコンの特長は加湿までできるところです。
明確にポジティブなニュアンスがある時は特長、そうでない時には特徴を用いると良いでしょう。
追求 / 追及 / 追究
追求と追及と追究では何を追い求めるかが異なります。
具体的な違いは以下のとおりです。
- 追求
ポジティブなものを追い求める
例:個人の自由を追求する。 - 追及
責任や欠点などを追い求める。
例:首相の責任を追及する。 - 追究
未知のものの正体を追い求める。
例:宇宙の謎を追究する。
不審 / 不信
不審と不信では以下のように意味が異なります。
- 不審
疑わしく思うこと
例:不審な男が店に入ってきた。 - 不信
人や物事を信じられないこと
例:大遅刻をして、上司から不信を買ってしまった。
「配付」と「配布」の違いのまとめ
以上、この記事では、配付と配布の違いについて解説しました。
- 配付
特定の人に配ること - 配布
不特定多数に配ること
配付と配布は似ているようでいて、明確な違いがあります。
忘れずに使い分けていきましょう。