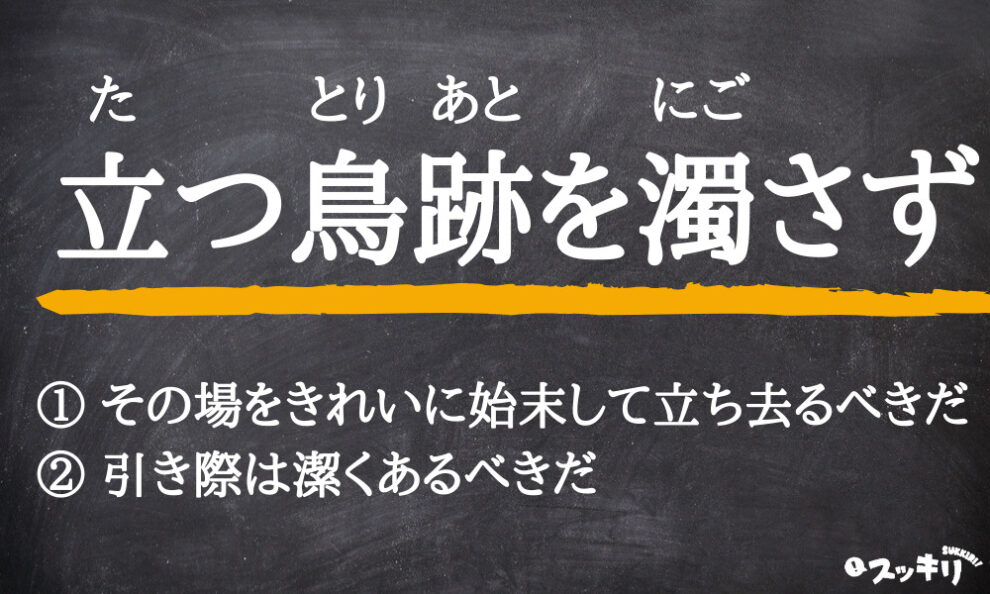「立つ鳥跡を濁さず」とは「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」「引き際は潔くあるべきだ」という意味です。
耳にしたことがあっても、「正確な意味がわからない」という方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では「立つ鳥跡を濁さず」の意味や使い方、由来、類義語などについて詳しく解説します。
☆「立つ鳥跡を濁さず」をざっくり言うと……
| 読み方 | 立つ(たつ)鳥(とり)跡(あと)を濁さず(にごさず) |
|---|---|
| 意味 | ①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ ②引き際は潔くあるべきだ |
| 由来 | 江戸時代のことわざ集から |
| 類義語 | 鷺は立ちての跡を濁さず 鳥は立てども跡を濁さず 原状回復 など |
| 対義語 | 後ろ足で砂をかける 後は野となれ山となれ 先は野となれ山となれなど など |
| 英語訳 | It is a foolish bird that defiles its own nest. (自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) It is a dirty bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) It is a ill bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) など |
このページの目次
「立つ鳥跡を濁さず」の意味
- その場をきれいに始末して立ち去るべきだ
- 引き際は潔くあるべきだ
「立つ鳥跡を濁さず」には、上記2つの意味があります。
以下、1つずつ詳しく見ていきましょう。
意味①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ
「立つ鳥跡を濁さず」の1つ目の意味は、「立ち去る者は、その場をきれいに始末してから離れるべきだ」というものです。
「立つ鳥」と「跡を濁さず」には、それぞれ以下のような意味があります。
- 立つ鳥
飛び立つ水鳥 - 跡を濁さず
飛び立った跡が濁っておらず、澄んでいる
つまり、「立つ鳥跡を濁さず」は、「水鳥が水辺を汚さずに飛び立つ」という様子を表しています。

水鳥は、季節ごとにいろいろな場所を転々とします。
その際、滞在した水辺を汚さずに飛び立つという特徴があります。
したがって、「立つ鳥跡を濁さず」は、「水鳥のように、その場をきれいに始末してから立ち去るべきだ」という言葉なのです。
意味②引き際は潔くあるべきだ
「立つ鳥跡を濁さず」には、「引き際は潔くあるべきだ」という意味もあります。
この意味は、1つ目の意味「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」が転じたものです。
「その場を汚さずに立ち去ること」が、以下のような状態のたとえになっているのです。
- 後悔や未練が残っていない状態
- 後始末をしっかり終えて、やり残している作業がない状態
「引き際は潔くあるべきだ」という意味で「立つ鳥跡を濁さず」を使う場面としては、ビジネスシーンが多いです。
以下のような言い回しは、「立つ鳥跡を濁さず」の誤用です。
× 飛ぶ鳥跡を濁さず
× 立つ鳥は跡を濁さず
× 立つ鳥は跡を濁さない
ただし、「飛ぶ鳥跡を濁さず」は使う人が増えているため、「立つ鳥跡を濁さず」の言い換え表現として定着しつつあります。
「立つ鳥跡を濁さず」の価値観
「立つ鳥跡を濁さず」が表す「汚さずにその場を立ち去るべき」「潔く引くべき」という精神は、日本で重んじられている価値観といえます。
たとえば武道では、礼節を守ることや、勝負の結果を潔く認めることが重要視されています。
しかし、「立つ鳥跡を濁さず」の考え方は、日本だけのものではありません。
他の国でも、「立つ鳥跡を濁さず」の精神は好意的に受け止められます。
「立つ鳥跡を濁さず」の使い方
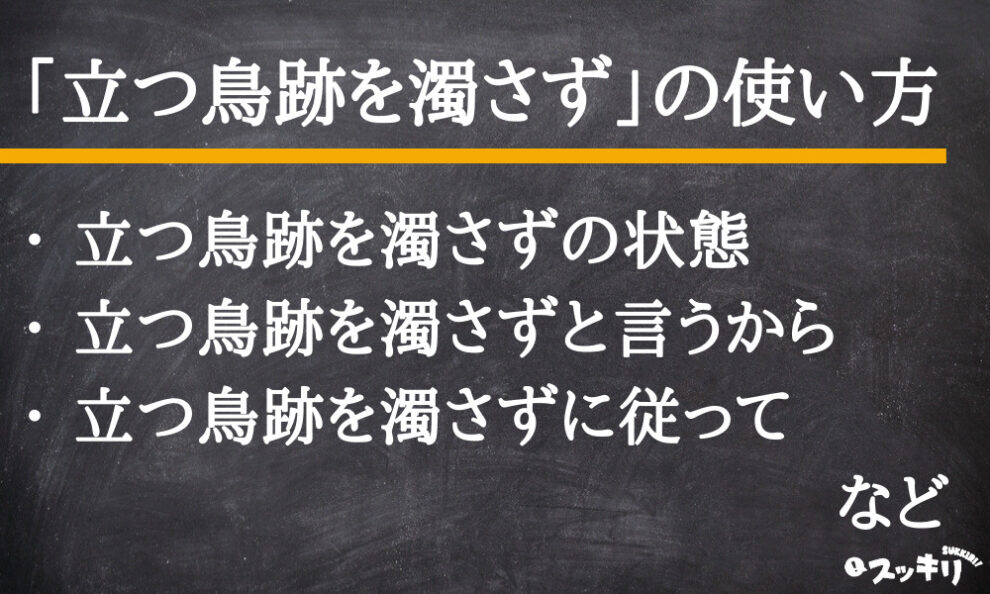
「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような言い回しで使います。
- 立つ鳥跡を濁さずの状態
- 立つ鳥跡を濁さずと言うから
- 立つ鳥跡を濁さずに従って
- 立つ鳥跡を濁さずという表現に匹敵する
- 立つ鳥跡を濁さずのとおり
- 立つ鳥跡を濁さずの精神
- 立つ鳥跡を濁さずだ
- 立つ鳥跡を濁さずといった様子
ここからは、2つの意味に分けて、「立つ鳥跡を濁さず」を使うシチュエーションや例文を解説します。
- その場をきれいに始末して立ち去るべきだ
- 引き際は潔くあるべきだ
それぞれ見ていきましょう。
使い方①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ
「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」という意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような場面で使います。
- 使用した場所を汚さずに立ち去るとき
- やるべき作業をすべて始末するとき
具体的な例文を見てみましょう。
- 彼女が出て行ったあとの部屋は、忘れ物がないだけでなく、ほこりさえも落ちていなかった。まさに、立つ鳥跡を濁さずの状態だった。
- 立つ鳥跡を濁さずと言いますから、野外フェスに参加したあとは、ゴミのポイ捨てをしないようにしましょう。
- 立つ鳥跡を濁さずに従って、今月すべき作業は、今月中にすべて終わらせよう。
- 彼女は別の部署に異動する前、私に仕事を素早く丁寧に引き継いでくれた。立つ鳥跡を濁さずという表現に匹敵する。
上記の例文のように、この意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、日常生活からビジネスシーンまで、幅広く使うことができます。
使い方②その場をきれいに始末して立ち去るべきだ
「引き際は潔くあるべきだ」という意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような場面で使います。
- 文句を言わずに組織から抜けるとき
- 未練や後悔を残さずに組織から抜けるとき
具体的な例文を見てみましょう。
- 最後まで社長に対する不信感は消えなかったが、立つ鳥跡を濁さずのとおり、余計なことは言わずに退職した。
- アルバイト先の閉店まであと1週間だ。ここで働けなくなるのは寂しいが、立つ鳥跡を濁さずの精神で、未練を口にするのはやめよう。
- A:彼は今の部署を気に入っていたのにも関わらず、潔く異動を受け入れたそうだ。
B:立つ鳥跡を濁さずだね。 - 彼らは、きちんと話し合ったうえで、「恋人としての関係を終える」という決断に至った。お互いに立つ鳥跡を濁さずといった様子だった。
例文からもわかるとおり、この意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、ビジネスシーンで使うことが多いです。
しかし、恋愛の別れで使うこともあります。
「立つ鳥跡を濁さず」の由来
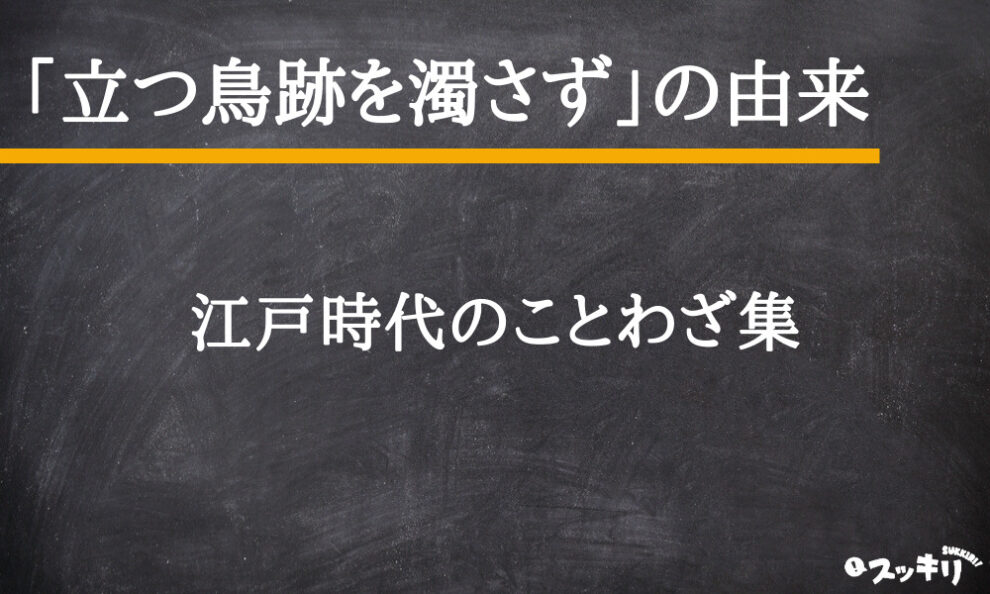
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざは、江戸時代のことわざ集から生まれました。
「立つ鳥跡を濁さず」と同じようなことわざは、安土桃山時代のころにすでに存在していました。
たとえば、『北条氏直時分諺留(ほうじょううじなおじだいことわざどめ)』には、「鷺(さぎ)はたちての跡濁さぬ」という言葉が登場しています。
「鷺は、飛び立っても跡を汚さない」という意味ですから、「立つ鳥跡を濁さず」と同じことを表していますね。
その後、江戸時代のことわざ集では、「立つ鳥跡を濁さず」という表現が使われるようになったのです。
「立つ鳥跡を濁さず」の「鳥」がどの鳥を指しているかという点には、2つの説があります。
- 鷺だという説
『北条氏直時分諺留』では「鷺はたちての跡濁さぬ」と記載されていたため
さまざまな鷺の種類が各季節に日本に飛来するため - 白鳥だという説
春・秋に日本に飛来する身近な鳥であるため
「立つ鳥跡を濁さず」の類義語
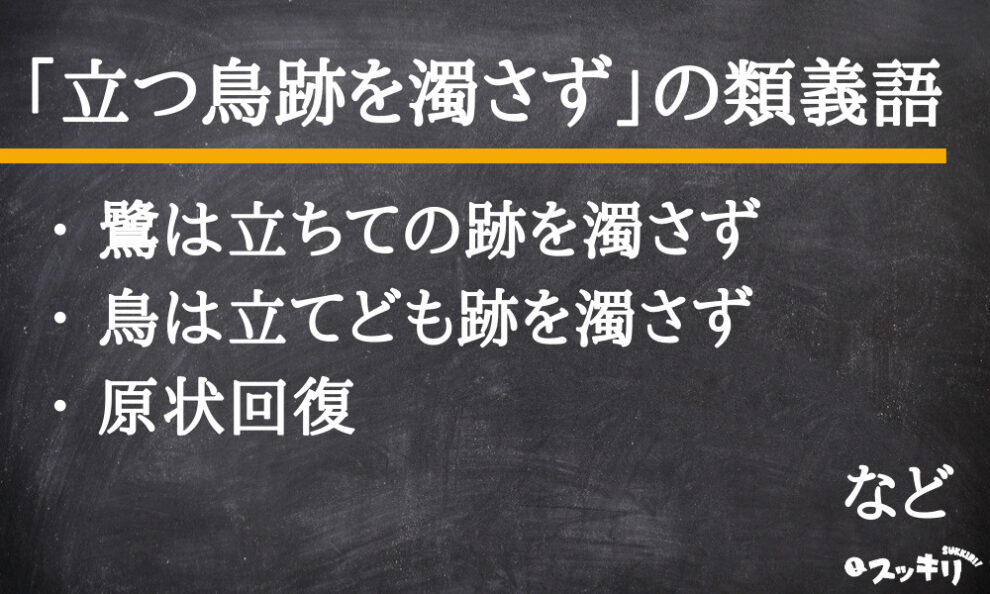
「立つ鳥跡を濁さず」には以下のような類義語があります。
- 鷺(さぎ)は立ちての跡を濁さず
潔く退くこと - 鳥は立てども跡を濁さず
元通りの状態にして去ること - 原状回復(げんじょうかいふく)
本来の状態に戻すこと - 原状復帰(げんじょうふっき)
変化する前の状態に戻すこと - 後腐れ(あとくされ)なく
物事が終わったあとに面倒なことが残らない様子 - 元に戻す
元通りの状態にする
「立つ鳥跡を濁さず」の対義語
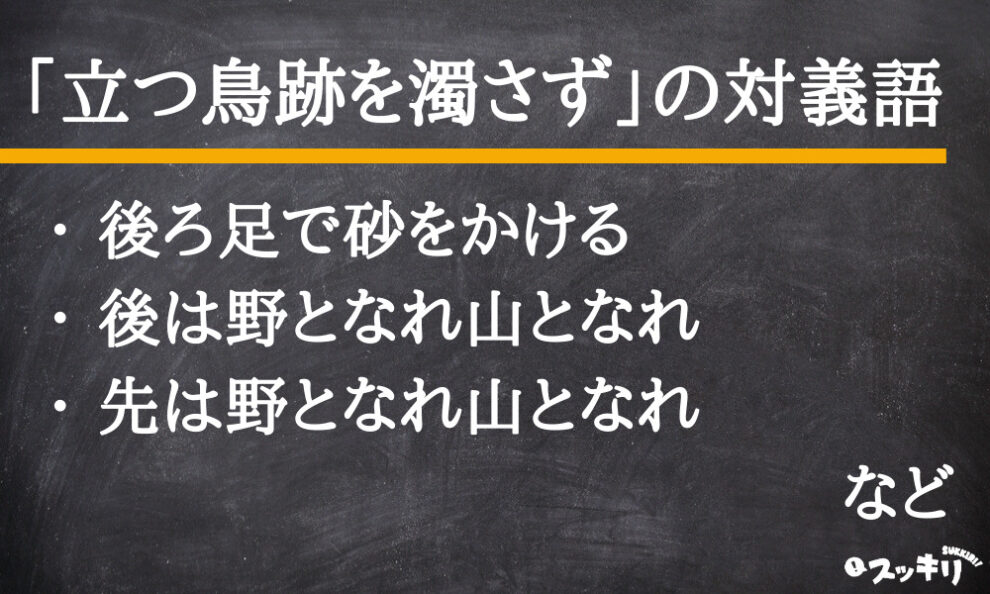
「立つ鳥跡を濁さず」には以下のような対義語があります。
- 後ろ足で砂をかける
人から受けた恩に報いず、裏切ること - 後は野となれ山となれ
やるだけのことはしたので、後はどうなっても仕方がない - 先は野となれ山となれ
やるだけのことはしたので、後のことはどうなっても仕方がない - 末は野となれ山となれ
やるだけのことはしたので、後のことはどうなっても仕方がない - 旅の恥は掻き捨て(かきすて)
旅先では知り合いがいないので、恥ずかしいことを平気でやってしまう - 旅の恥は弁慶状(べんけいじょう)
旅先では知り合いがいないので、恥ずかしいことを平気でやってしまう
「立つ鳥跡を濁さず」は「後始末をしっかりする」「潔く退く」という意味があります。
つまり、「立つ鳥跡を濁さず」は人に迷惑をかけないことを表します。
そのため、秩序を乱すような言動を表す言葉が、「立つ鳥跡を濁さず」の対義語となります。
「立つ鳥跡を濁さず」の英語訳
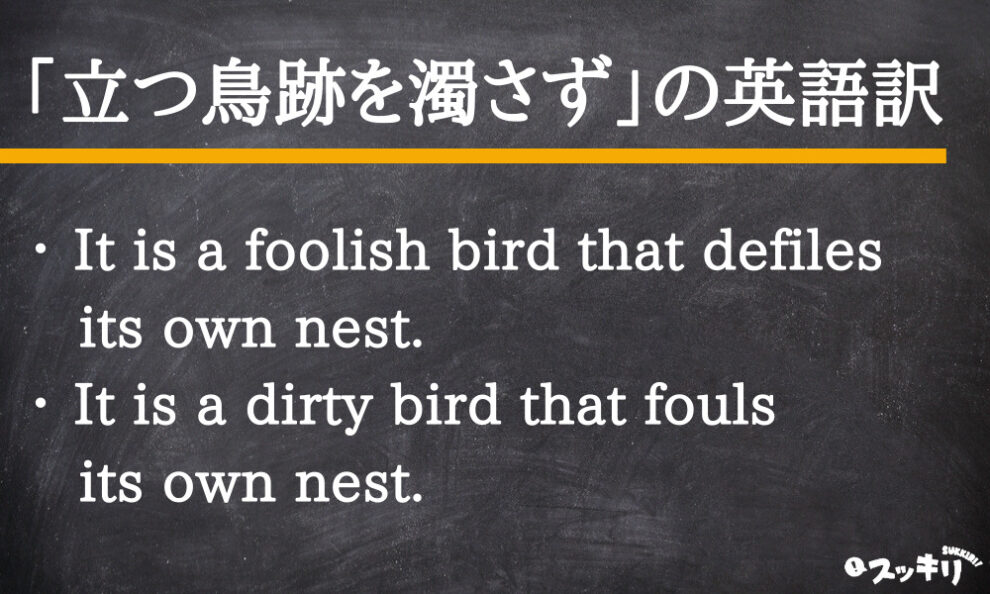
「立つ鳥跡を濁さず」を英語に訳すと、次のような表現になります。
- It is a foolish bird that defiles its own nest.
(自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) - It is a dirty bird that fouls its own nest.
(自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) - It is a ill bird that fouls its own nest.
(自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) - Cast no dirt into the well that gives you water.
(あなたに水を与える井戸に、ゴミを捨てるな。)
これらの英語訳は、「潔く退く」という意味合いは含まれていませんから、注意しましょう。
すべて、単に「身の回りを清潔にしましょう」ということのみを表しています。
「立つ鳥跡を濁さず」の中国語訳
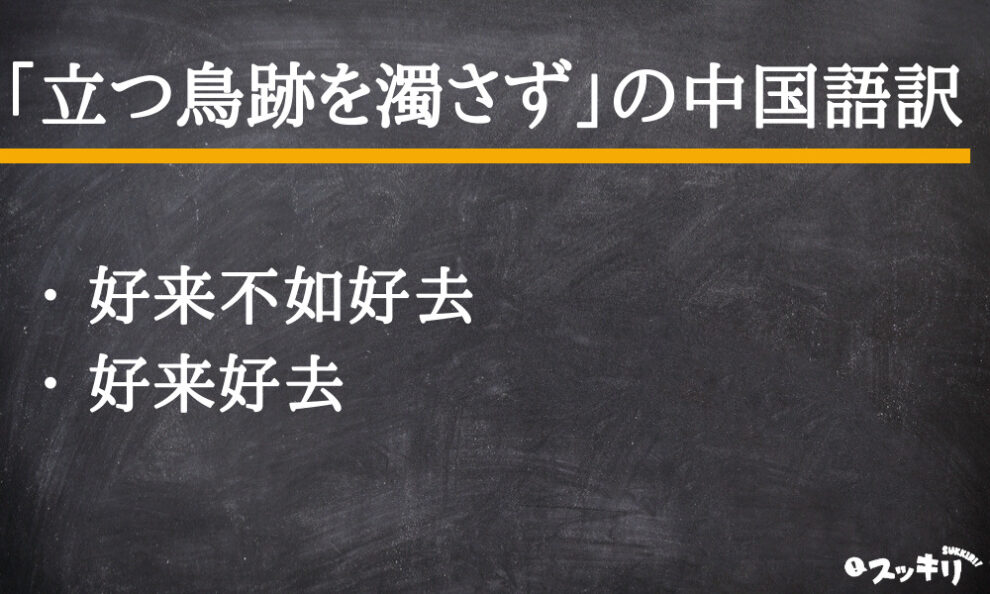
「立つ鳥跡を濁さず」を中国語に訳すと、次のような表現になります。
- 好来不如好去
(良い始め方をすることよりもむしろ、良い終わり方をすることのほうが大切だ) - 好来好去
(最初から最後まで、まっとうすべきだ)
“好来不如好去” の意味を詳しく
“好来不如好去” は、「立つ鳥跡を濁さず」と同じ意味をもつ言葉です。
読み方をカタカナに表すと、「ハオライブールーハオチュー」となります。
“好来好去” の意味を詳しく
“好来好去” は、「最後だけでなく、最初も同じようにしっかりとしなければいけない」という意味であるため、最後に重点をおく「立つ鳥跡を濁さず」とは少し異なります。
“好来好去” の読み方をカタカナに表すと、「ハオライハオチュー」となります。
「立つ鳥跡を濁さず」を実現するための心がけ
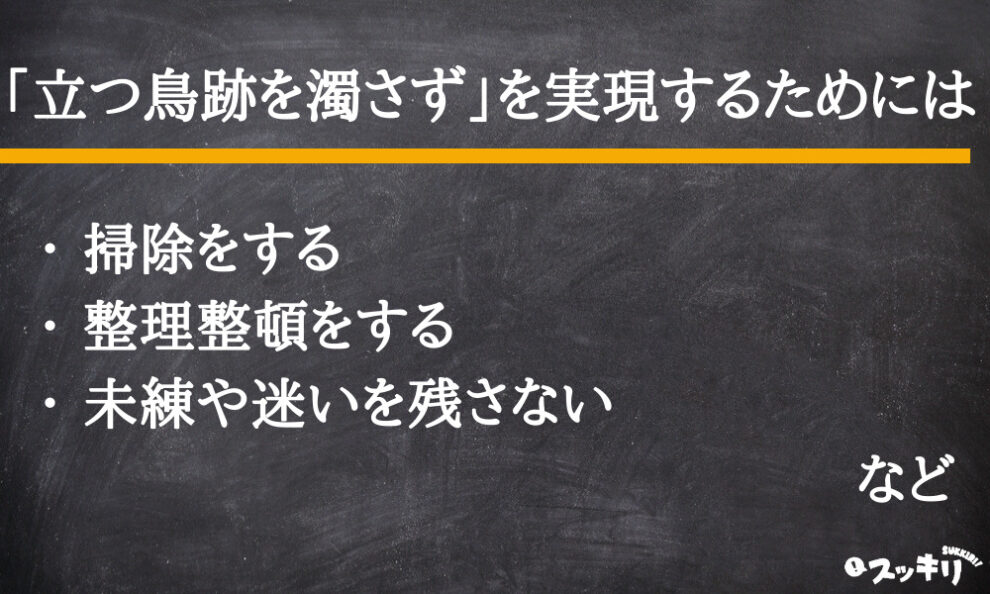
「立つ鳥跡を濁さず」は、「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」「引き際は潔くあるべきだ」という2つの教訓を表しています。
しかし、具体的にはどのようなことをすれば「立つ鳥跡を濁さず」になるのか、イメージできないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、この見出しでは、「立つ鳥跡を濁さず」を実現するための心がけについて、それぞれ解説します。
①その場をきれいに始末して立ち去るための心がけ
その場をきれいに始末して立ち去るためには、まず以下のようなことに気をつけましょう。
- 掃除をする
- 整理整頓をする
また、会社を辞めたり、部署を異動したりするときは、以下のような始末も大切です。
- 上司に早めに連絡する
(自分の意思である場合) - 退職前に仕事を引きつぐ
- 備品の返却
(名刺・社員証・制服・鍵など) - 残っている有給休暇を消化する
ちなみに、大学卒で、入社から3年以内に離職する人は約3割といわれています。
突然「辞めます」と言ったり、引き継ぎをせずに辞めてしまったりすると、周囲に迷惑がかかってしまいます。
そのため、「立つ鳥跡を濁さず」を目指して、計画的にやるべきことを終わらせましょう。
②引き際を潔くするための心がけ
引き際を潔くするためには、以下のようなことに気をつけましょう。
- 未練や迷いを残さない
- 退くことが決まったら勢いよく辞める
- お世話になった人に感謝を述べる
仕事でも恋愛でも、上記のような点を意識することが重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」のまとめ
以上、この記事では「立つ鳥跡を濁さず」について解説しました。
| 読み方 | 立つ(たつ)鳥(とり)跡(あと)を濁さず(にごさず) |
|---|---|
| 意味 | ①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ ②引き際は潔くあるべきだ |
| 由来 | 江戸時代のことわざ集から |
| 類義語 | 鷺は立ちての跡を濁さず 鳥は立てども跡を濁さず 原状回復 など |
| 対義語 | 後ろ足で砂をかける 後は野となれ山となれ 先は野となれ山となれなど など |
| 英語訳 | It is a foolish bird that defiles its own nest. (自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) It is a dirty bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) It is a ill bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) など |
「立つ鳥跡を濁さず」の意味からは、人に迷惑をかけないことの大切さがわかります。
日常生活やビジネスシーンで、「立つ鳥跡を濁さず」の精神を心がけましょう。