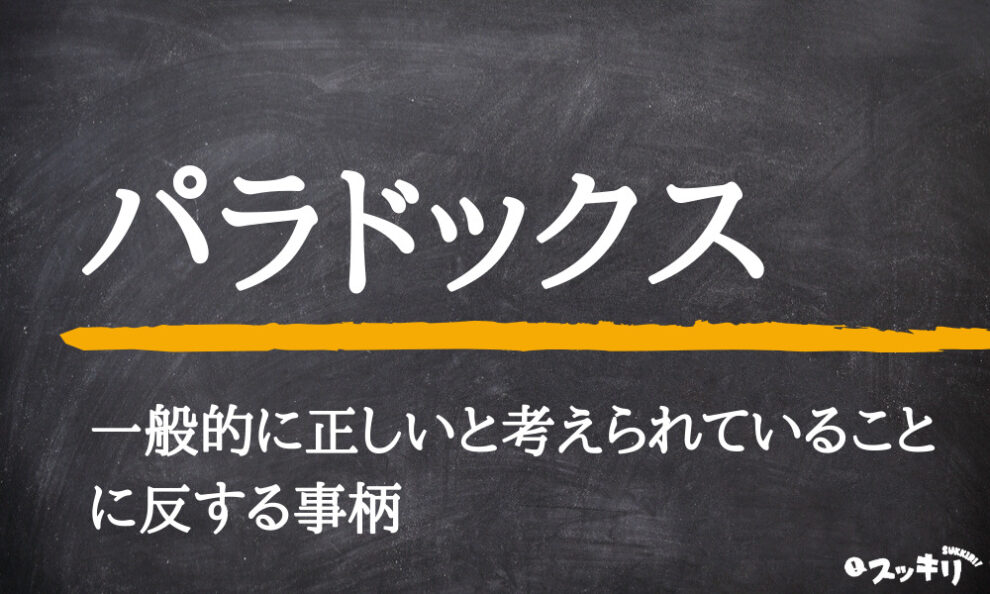パラドックスとは「一般的に正しいと考えられていることに反する事柄」という意味です。
よく使われる言葉ですが、意味が複雑なので理解しきれていない人も多いでしょう。
この記事では具体例を挙げながら意味を分かりやすく解説します。
☆「パラドックス」をざっくり言うと……
| 英語表記 | パラドックス(paradox) |
|---|---|
| 意味 | 一般的に正しいと考えられていることに反する事柄 |
| 語源 | 「反対の意見」を意味するギリシャ語 “para” と “doxa” |
| 類義語 | 逆説 背理など |
「パラドックス」の意味
一般的に正しいと考えられていることに反する事柄
例:解説できないパラドックスが生じている。
パラドックスには、大きく分けると以下の2つの意味があります。
- 論理的に矛盾しているもの
- 直観的には受け入れがたいが、論理的矛盾ではないもの
「論理的に矛盾しているもの」という意味
単に、「論理的に矛盾しているもの」とは言っても、以下のような意味があります。
- 一般的に正しいと考えられていることに反する事柄
- 一見矛盾しているにもかかわらず、よく考えると一種の真理であること
- ある命題と、それを否定する命題が共に成り立つと結論され、その推論の中に誤りがあることを明確に指摘できないこと
- 世の中の理に反する説であるにもかかわらず、その説が誤りである正当な論拠を見いだしがたいもの
この意味が狭義のパラドックスです。
パラドックスは、簡単に言うと「正しそうにも、正しくなさそうにも見えること」を表す言葉です。
「直観的には受け入れがたいが、論理的矛盾ではないもの」という意味
パラドックスには、直観的には受け入れがたいが、論理的矛盾ではないものという意味があります。
つまり、実際には論理的に矛盾はしていないものの、世間一般の感覚では受け入れにくいことを表すものです。
こちらは、広義の意味でのパラドックスになります。
「直観的には受け入れがたいが、論理的矛盾ではないもの」という意味のパラドックスは、擬似パラドックス(pseudoparadox)と言われます。
実際には論理矛盾をしていないという点で、本来のパラドックスの意味とは異なっています。
「パラドックス」の具体例
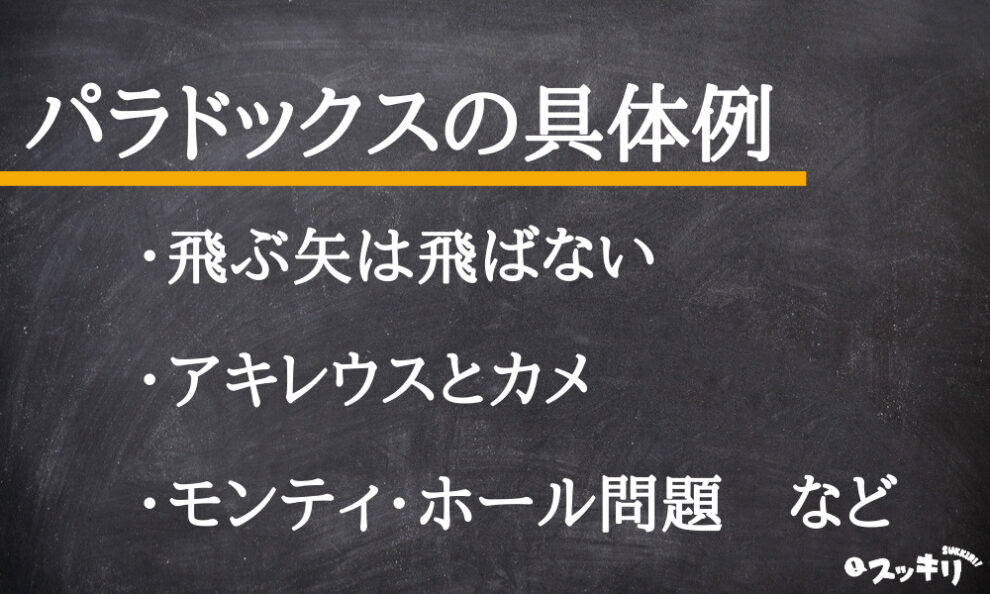
パラドックスには、狭義の意味でのパラドックスと、広義の意味での擬似パラドックスが存在します。
それぞれの分野で有名なパラドックスの例をいくつか挙げていきます。
狭義のパラドックス
古代ギリシアの哲学者であるゼノンが唱えた有名なパラドックスを2つ紹介します。
- 飛ぶ矢は飛ばない
- アキレウスとカメ
「飛ぶ矢は飛ばない」とは
飛んでいる矢を一瞬一瞬に注目して見ると、矢が止まっているという結論がでてしまうパラドックスです。
飛んでいる矢を1秒間見ると大きく移動していることがわかります。
しかし、見る時間を極限まで少なくしたとき、矢が運動をしていない瞬間として切り取ることができてしまいます。
つまり、停止の連続を繰り返す矢は運動をしていないという結論になってしまうというパラドックスです。
近代数学では無限の概念を用いずに極限・収束・連続等を定義することによってこのパラドックスを回避しています。
つまり、極限まで短い時間を切り取ろうとしても、ほんのわずかにでも矢は運動をしてしまうという考えです。
「アキレスとカメ」とは
アキレスが、自分よりも移動速度の遅いカメに永久に追いつけないというパラドックスです。
アキレスとカメが同時に出発し、アキレスは後方からカメを追いかけます。
アキレスはカメよりも速い速度で移動することができるため、すぐにスタート時にカメがいた場所まで到達します。
しかし、そのころにはカメはアキレスよりわずかに前方の地点まで進んでいます。
そして、その地点までアキレスが到達したときには、またわずかにカメが前方まで進むのです。
この繰り返しを考えていくと、アキレスは永久にカメに追いつくことができないのです。
広義の擬似パラドックス
擬似パラドックスは、主に数学の分野で用いられる言葉で、以下のような具体例が挙げられます。
- モンティ・ホール問題
- 誕生日のパラドックス
「モンティ・ホール問題」とは
モンティ・ホール問題とは、当たりのドアを当てる問題から生じるパラドックスです。
プレーヤーの前に閉じた3つのドアがあって、当たりのドアが1つだけあり、他の2つははずれです。
プレーヤーが当たりのドアを当てると景品がもらえるゲームです。
プレーヤーが1つのドアを選択した後、司会のモンティが残りのドアのうちはずれのドアをひとつ発表します。
このタイミングで、プレーヤーは最初に選んだドアを、残っている開けられていないドアに変更する権利が与えられます。
ここでプレーヤーはドアを変更したほうが当たりの確率が上がるのかという問題です。
この問題の答えは、「ドアを変更したほうがいい」になります。
不正解のドアが開けられた時点で、どちらを選んでも正解の確率は半分ずつだと直感的には感じられます。
しかし、実際にはドアを変更すると2/3の確率で正解できるのです。
この問題はアメリカのテレビ番組で行われたゲームでしたが、視聴者の多くがこの答えに納得できませんでした。
番組に向けた抗議文が何通も送られてくるなどの大きな流れに発展し、擬似パラドックスの代表例になりました。
「誕生日のパラドックス」とは
誕生日のパラドックスとは、「何人集まれば、その中に誕生日が同じ人が2人以上いる確率が、50%を超えるか?」という問題によって引き起こされるパラドックスです。
当然ですが、366人が集まれば同じ誕生日の人がいる確率は100%となります。
しかし、実は70人しか集まらなくても確率は99.9%を超え、23人を超えれば確率は50%を超えるのです。
数学的な考えをもとにすれば、この答えは矛盾しないのですが、直感的な感覚では納得できないと思います。
これらの問題がパラドックスと言われるのは、正解が一般的な直感と反しているという理由からです。
論理的な矛盾が生じているためパラドックスと言われているわけではないという点に注意しましょう。
ビジネスでも使える「パラドックス」の事例
上記で挙げたようなクイズや物語としてのパラドックス以外に、生活に応用できるパラドックスが存在します。
- 予防医学のパラドックス
- 成長のパラドックス
それぞれの意味を詳しく解説します。
「予防医学のパラドックス」の意味
予防医学では、「リスクが小さい多数の集団は、リスクが大きい少数の集団よりも患者の数が多い」というパラドックスがあります。
予防医学とは、健康な人を対象に行う医学のことです。
病気などになって症状が出てからではなく、病気になる前の人に対して予防を行います。
リスクが大きい集団では、リスクが小さい集団よりも、すでに高血圧になっている人が多いと考えられます。
すでに高血圧だと診断されている人は予防医学の対象になる患者ではありません。
そのため、健康な人が多い集団ほど、予防医学の対象になる患者が多くなるのです。
たとえば、ある集団の全員が塩分摂取をひかえれば、高血圧の患者が少なくなります。
逆に重度の高血圧の人を一人だけを手厚く治療しても、高血圧になる人の総数を大きく減らすことはできません。
つまり、病気になるリスクが小さい人に先に対策をするほうが、健康水準は高くなりやすいのです。
「成長のパラドックス」の意味
経済においては、「デフレから脱却すると、実質GDP成長率が伸びなくなる」というパラドックスが存在します。
デフレとは、物価が下落し続けることで、企業の倒産、失業者の増大など不況や社会的不安を伴うことが多いです。
つまり、デフレは景気が悪い状態というイメージです。
実質GDPの成長率は、その国の経済成長の度合を測る指標のひとつです。
1人あたりの実質生産性の伸び率と就業者数の伸び率の合計として求められます。
つまり、デフレから脱却して景気が良くなったにも関わらず、国の経済成長の度合は低く見積もられてしまうという矛盾が生じるのです。
デフレの状態では景気の悪化により失業者が増えますが、デフレから脱却すれば雇用が増えて失業者が減ります。
実質GDPの成長率は、1人あたりの実質生産性の伸び率と就業者数の伸び率の合計として求められます。
そのため、多くの失業者の就職が決まり切ってしまうことで就業者の伸びが鈍化すると、実質GDP成長率が鈍るのです。
「パラドックス」の使い方
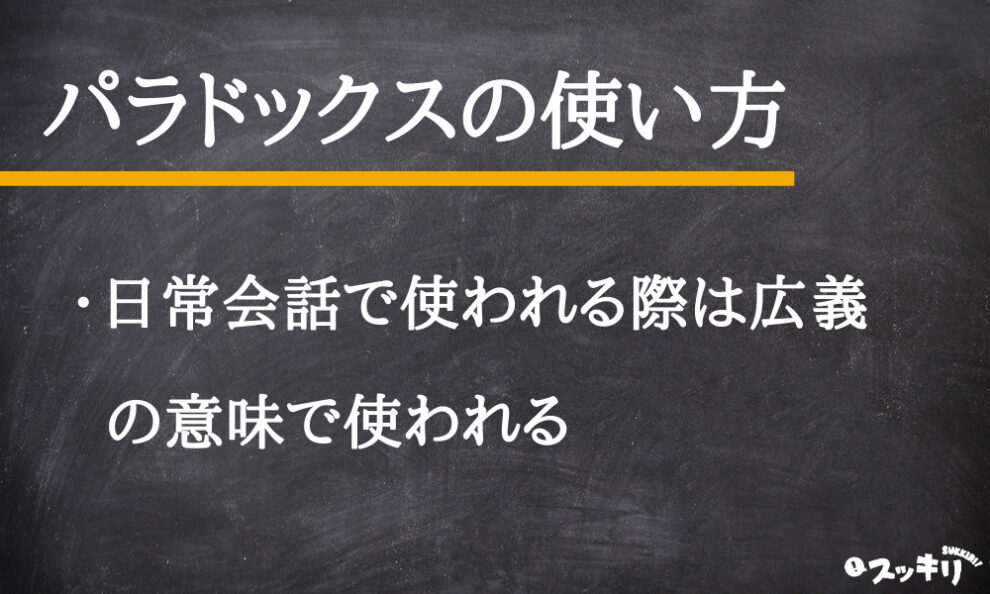
日常会話で使われるパラドックスは、「直観的には受け入れがたいが、論理的矛盾ではないもの」という広義の意味で使われることが多いです。
- パラドックスによって頭がこんがらがってきた。
- 複雑なパラドックスを考えることで、ギリシアの哲学は発展した。
- アキレスとカメのパラドックスは有名だ。
「パラドックス」の語源
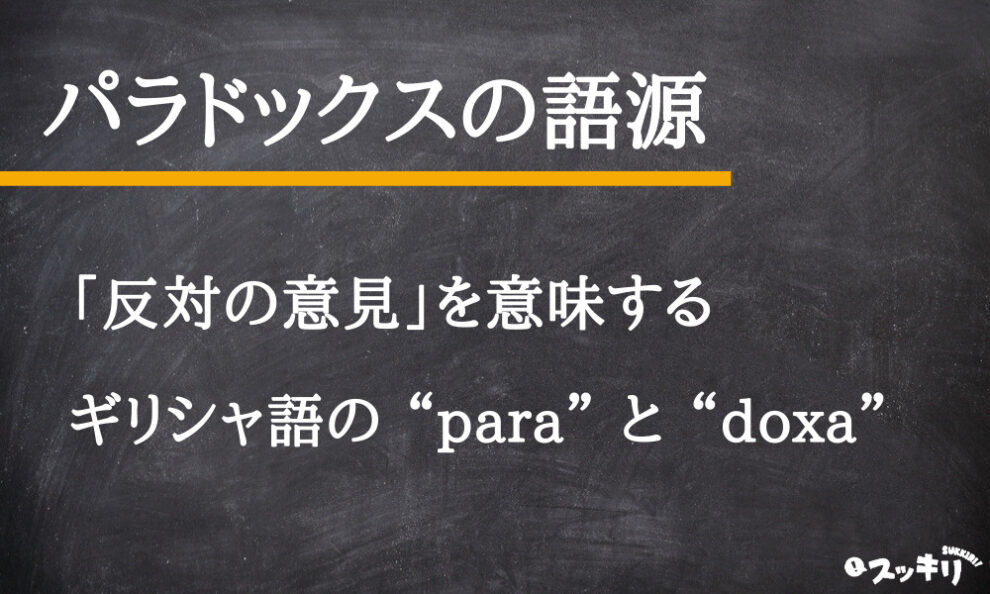
「パラドックス」の語源はギリシャ語の “para” と “doxa” です。
それぞれには以下の意味があります。
- para
反対 - doxa
通念・意見
ここから “paradox” という英単語が生まれました。
“paradox” の意味は、カタカナ語のパラドックスと同じ意味です。
「パラドックス」の類義語
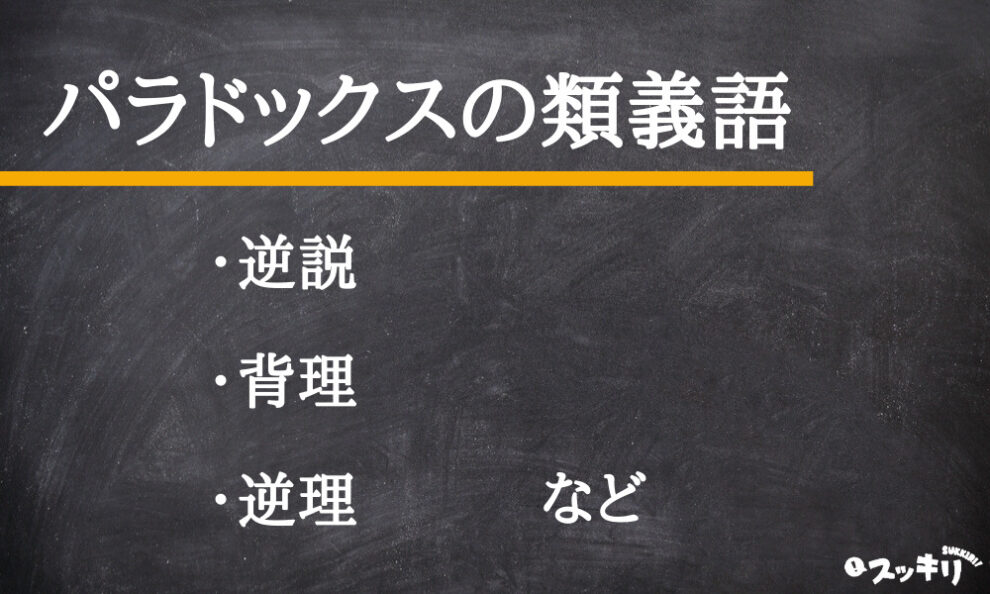
パラドックスには以下のような類義語があります。
「逆説」「背理」「逆理」などの言葉は、パラドックスと同じ意味で使われます。
「パラドックス」と「ジレンマ」の違い
パラドックスとジレンマの違いは、以下のようになります。
- パラドックス
矛盾することがらが同時に成り立つこと - ジレンマ
矛盾することがらの間で板挟みになること
つまり、「板挟みになって葛藤する」という要素があるかないかが相違点になります。
「パラドックス」と「矛盾」の違い
矛盾とは、「つじつまが合っていないこと」を広く表す言葉です。
それに対して、パラドックスは「一見正しいように見えるが、矛盾していること」を表す言葉です。
つまり、パラドックスは単に矛盾が起きているだけでなく、矛盾が起きているにもかかわらず、それが正しいように感じられてしまうという意味を持つのです。
「パラドックス」のまとめ
以上、この記事ではパラドックスについて解説しました。
| 英語表記 | パラドックス(paradox) |
|---|---|
| 意味 | 一般的に正しいと考えられていることに反する事柄 |
| 語源 | 「反対の意見」を意味するギリシャ語 “para” と “doxa” |
| 類義語 | 逆説 背理など |
具体例をみることで、パラドックスの意味を掴むことができましたね。