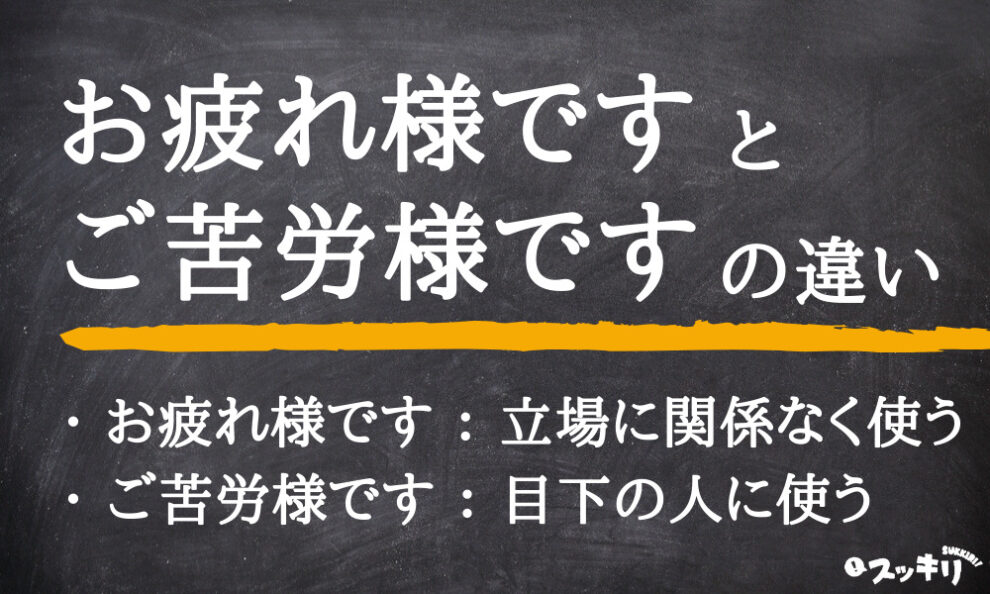「お疲れ様です」と「ご苦労様です」は、「お疲れ様」は、相手の立場に関係なく使うが、「ご苦労様」は目下の人に対して使うという点が異なります。
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」はどちらも相手をねぎらう言葉であるため、違いがわかりづらいですよね。
しかし、だからといって曖昧に使い分けてしまうのは危険です。
特にビジネスシーンで、両者を混同してしまうと、悪気はなくても相手に失礼になってしまうおそれがあります。
そこで、この記事では、「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いや、それぞれの使い方について詳しく解説します。
また、同じく違いがわかりづらい「お世話様です」の意味も紹介します。
このページの目次
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違い
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」は、どちらも相手を気にかけ、ねぎらう挨拶です。
しかし、使い方において下記のような違いがあります。
- お疲れ様です
相手の立場に関係なく使うことができる - ご苦労様です
目上の人から目下の人に対してのみ使う
「お疲れ様です」は、目下の人が目上の人に対して使っても問題ありません。
しかし、「ご苦労様です」は、目下の人が目上の人に使うと失礼になってしまうのです。
「お疲れ様です」の意味
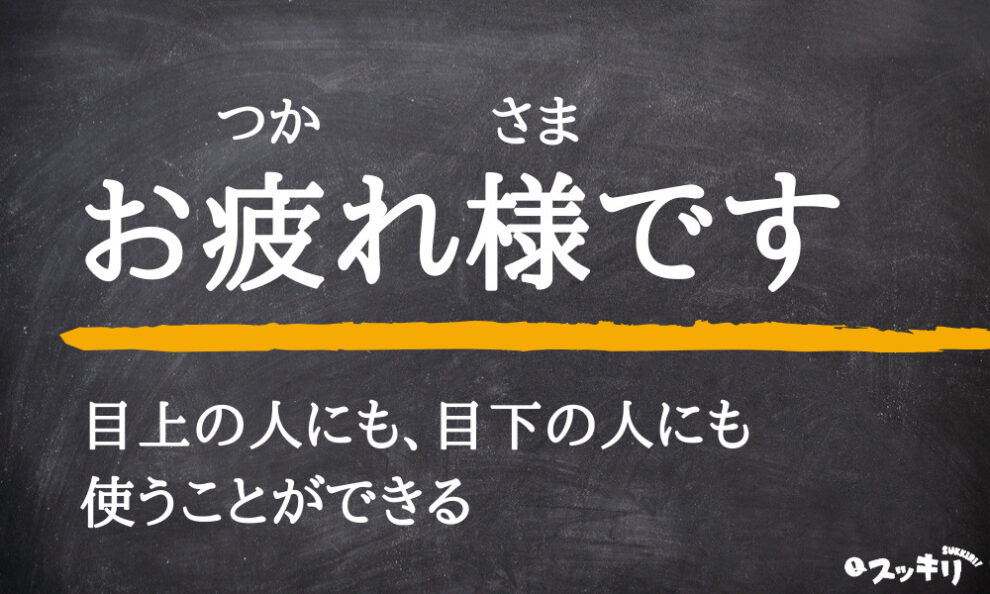
「お疲れ様です」は、相手をいたわる言葉です。
目上の人にも、目下の人にも使うことができます。
もちろん、同僚など、同じ立場の人どうしでも「お疲れ様」と使うことができます。
また、職場において「お疲れ様です」は、相手をいたわる意味合いだけではなく、単なる挨拶としても使われます。
現在、「お疲れ様です」は、立場に関係なく使われます。
しかし、1990年代までは、主に目上の人が目下の人に対してのみ使う言葉でした。
たとえば、1997年の『新明解国語辞典第五版』で「お疲れ様です」は、上の立場の人が使うあいさつとして説明されていました。
上下関係を気にせずに使われるようになったのは、2000年代からです。
「お疲れ様です」の使い方
「お疲れ様です」は、おもに下記の場面で使います。
- 相手をねぎらうとき
- 職場で挨拶をするとき
それぞれの場面に分けて例文を紹介します。
①相手をねぎらうとき
相手をねぎらう場面で、「お疲れ様です」は以下のように使います。
- 〇〇くん、今日も出張お疲れ様です。
- △△ちゃん、試合お疲れ様!
- お疲れ!このあとどこか遊びに行こうよ!
- 先輩、受験勉強お疲れ様です。
友人など親しい相手に使うときには、例文②③のように、「お疲れ様」「お疲れ」とカジュアルな言い回しになることが多いです。
②職場で挨拶をするとき
職場で挨拶をするとき、「お疲れ様です」は以下のように使います。
- (オフィス内ですれ違って)
A:お疲れ様です。
B:お疲れ様です。 - (相手に声をかけるときの第一声として)
A:お疲れ様です。Cさんはどこにいらっしゃいますか?
B:いま席を外していますよ。 - (メールの文面で)
お疲れ様です。総務部の〇〇です。予算表をこちらのメールに添付して送信します。 - (退勤時に)
A:お疲れ様です。
B:お疲れ様です!また明日。
ビジネスシーンでの注意点
ビジネスシーンで「お疲れ様です」と使う際には、下記の点に気をつけましょう。
- 目上の人に使うと嫌がられる場合がある
- 社外の人には使わない
1つずつ見ていきましょう。
①上司に使うと嫌がられる場合がある
「お疲れ様です」は目上の人に使っても問題ない言葉です。
しかし、なかには、部下や後輩から「お疲れ様です」と言われるのを嫌がる人もいます。
1990年代までは、目上の人が目下の人に対して使うことが多かったため、特に年配の人は、部下から「お疲れ様です」と声をかけられることに慣れていないのです。
そのため、場合によっては「お疲れ様です」を下記のような言葉に言い換えましょう。
- (ねぎらうとき)
お疲れ様でございます - (先に退勤するとき)
お先に失礼します - (上司が外出先から帰ってきたとき)
お帰りなさいませ - (上司の退勤を見送るとき)
お気をつけてお帰りください - (すれ違ったり、前を通ったりするとき)
失礼いたします
「“お疲れ様でございます”は丁寧語の二重表現で、誤りなのではないか」と捉える人もいますが、実は正しい表現です。
「お疲れ様でございます」は、二重表現ではなく、以下のような構造になっているからです。
○お疲れ様+で(助詞)+ございます(丁寧語)
×お疲れ様です(丁寧語)+ございます(丁寧語)
このように、「お疲れ様でございます」は文法的にも間違っていない表現ですから、「お疲れ様です」をより丁寧にしたいときに使ってみましょう。
②社外の人には使わない
「お疲れ様です」は、社外の人には使うと失礼になってしまいます。
そのため、取引先や顧客などには、「お疲れ様です」の代わりに下記のような表現を使いましょう。
- 平素よりお世話になっております
- ご足労おかけしました
- ご足労いただきありがとうございます
- 本日はありがとうございました
「ご苦労様です」の意味
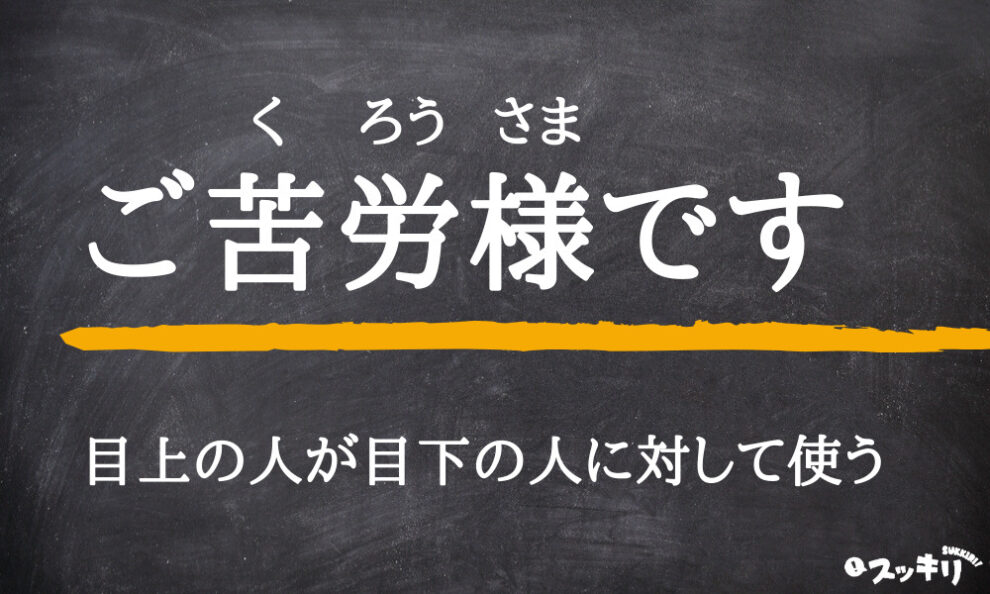
「ご苦労様です」は、相手の仕事や努力をねぎらう言葉で、目上の人が目下の人に対して使います。
目下の人が目上の人に対して使ってしまうと、失礼にあたるため注意しましょう。
「ご苦労様です」の使い方
「ご苦労様です」はおもにビジネスシーンで、上司が部下に対して使います。
例文を見てみましょう。
- 部下:プレゼン資料の準備ができました。
上司:ご苦労様です。あとで確認するので、机の上に置いておいてください。 - 部下:先ほど出張先から戻りました。
上司:遠くまでご苦労様。大変だったでしょう。 - みなさん、連日ご苦労様です。また年末に皆で飲み会でもしよう。
「ご苦労様です」は例文②のように、「ご苦労様」と簡略化したかたちで使うこともあります。
「ご苦労様です」は、ねぎらいを素直に表す言葉ですが、稀に皮肉や嫌味としてあえて使うこともあります。
(例)家庭を見捨てて仕事ばかりとは、ご苦労様です。
皮肉としての「ご苦労様です」は上下関係なく使いますが、相手を傷つける可能性があるため注意しましょう。
「ご苦労様です」よりも「お疲れ様です」のほうがよく使う?
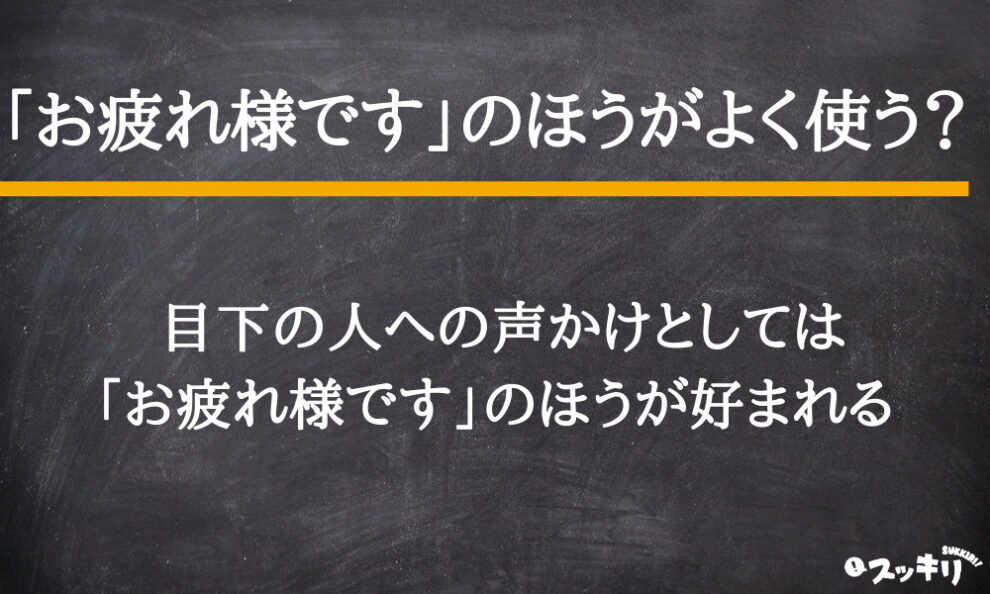
目上の人が目下の人をねぎらう場合、「ご苦労様です」と「お疲れ様です」のどちらを使っても問題はありません。
しかし、目下の人への声かけとしては「お疲れ様です」のほうが好まれる傾向があります。
たとえば、文化庁による「国語に関する世論調査」でも、下記のような結果が出ています。
- 2005年度の調査
仕事が終わった際のあいさつとして、「お疲れ様」を選ぶ人の割合が最も高くなった - 2015年度の調査
仕事後にかける言葉として、自分より目下の人にでも「お疲れ様」を使う人が61.4%となった
(「ご苦労様」を使うと答えた人はが28.4%)
また、秘書検定でも目下の人から目上に「お疲れ様です」を使い、目上の人から目下に「ご苦労様です」を使うということを定めています。
このように、「お疲れ様です」のほうが使い勝手が良いと考える人が多いのです。
その理由としては、以下のようにいくつかの説があります。
- 「時代劇の影響」という説
時代劇で、偉い人物が家臣に「ご苦労じゃった」「ご苦労であった」などと言うシーンが多いため、「ご苦労様です」は古いイメージが定着してしまい、現代で使うことに抵抗をもつ人が多い
※実際には、昔は「ご苦労じゃった」という言葉は存在しなかったと言われている - 「業界用語の影響」という説
テレビ局など、放送業界では立場や時間帯に関係なく、「お疲れ様です」という挨拶が多用されるため、使いやすい挨拶として一般の人々の生活にも定着した - 「疲労は誰もが感じるものだから」という説
立場に関係なく使いやすい
補足:「お世話様です」の意味
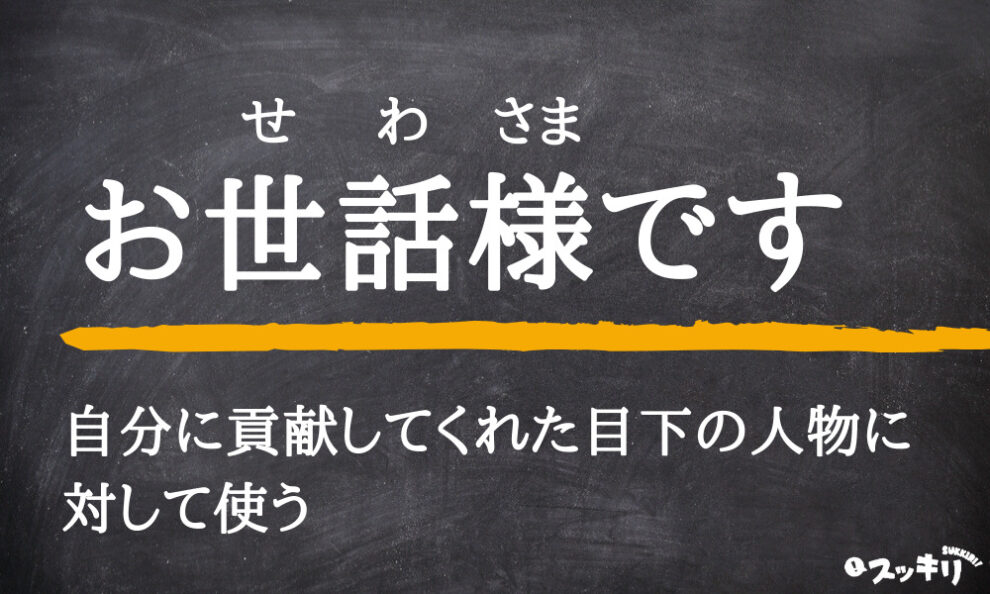
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」に似た言葉として、「お世話様です」があります。
「お世話様です」は、自分に貢献してくれた目下の人物に対して、感謝の気持ちを伝える言葉です。
目下の人に使うことが多いという点では、「ご苦労様です」のニュアンスに近いです。
しかし、「お世話様です」と「ご苦労様です」には、以下のような違いがあります。
- お世話様です
感謝のニュアンスが強い - ご苦労様です
ねぎらいのニュアンスが強い
なお、「お世話様です」は、普段からお世話になっている人への軽い挨拶としても使います。
「お世話様です」の使い方
「お世話様です」は、下記のようなときに使います。
- 自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき
- 普段お世話になっている人に挨拶をするとき
それぞれの場面に分けて、例文を見ていきましょう。
①自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき
自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき、「お世話様です」は以下のように使うことができます。
- ◯◯さん、お世話様です。
- お世話様です。昨日は助かりました。
②普段お世話になっている人に挨拶をするとき
「お世話様です」は、普段お世話になっている人に挨拶をするときにも使います。
- A:こんにちは、宅急便です。
B:はい、お世話様です。 - A:またのご来店お待ちしています。
B:いつもお世話様です!また来ますね。 - A:Bさん、お世話様です。
B:こちらこそ、いつもありがとうございます。
この意味での「お世話様です」は、例文①②のように、顔なじみの配達業者さんや、いつも行くお店の店員さんに対して使うことが多いです。
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いのまとめ
以上、この記事では、「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いについて解説しました。
- お疲れ様です
相手の立場に関係なく使うことができる - ご苦労様です
目上の人から目下の人に対してのみ使う
「お疲れ様です」と「ご苦労様です」を上手に使い分けましょう。