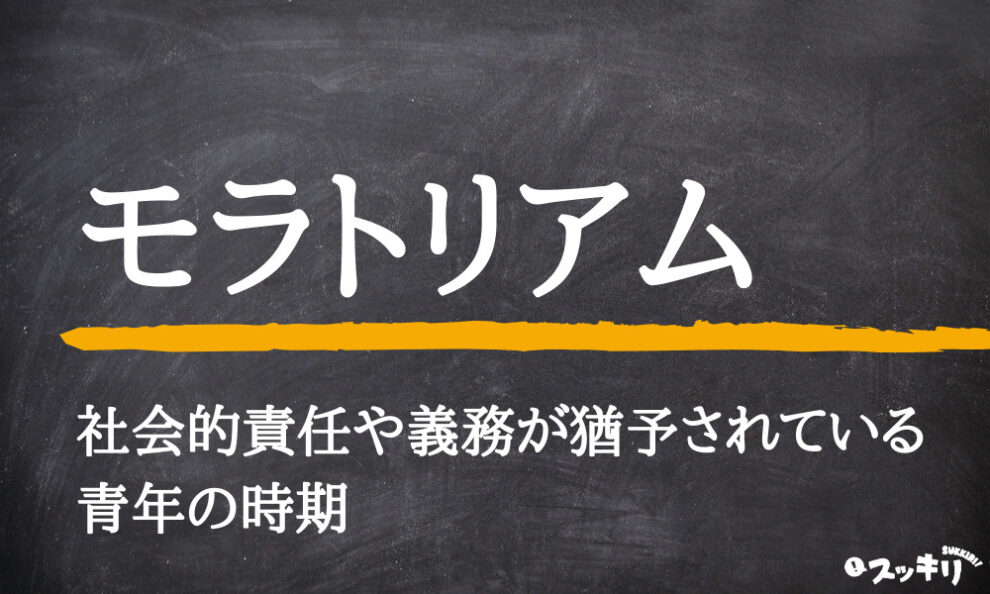モラトリアムとは「社会的責任や義務が猶予されている青年の時期」という意味です。
モラトリアムは心理学の分野で使われる言葉なので、難しい言葉かと思って敬遠してしまいますよね。
この記事では、モラトリアムの意味や語源について詳しく説明します。
☆「モラトリアム」をざっくり言うと……
| 英語表記 | モラトリアム(moratorium) |
|---|---|
| 意味 | 社会的責任や義務が猶予されている青年の時期 |
| 語源 | 「遅延」という意味のラテン語 “mora” |
| 類義語 | 猶予期間 免除期間など |
このページの目次
「モラトリアム」の意味
社会的責任や義務が猶予されている青年の時期
例:モラトリアムが延長されつつある。
モラトリアムは、心理学の分野で「社会的責任や義務が猶予されている青年の時期」という意味を持つ言葉です。
「青年が社会人になる前に使うことを社会的に認められている見習い期間」を表します。
青年期になると、多くの人は身体的・知能的には大人と同程度の能力を持つようになります。
しかし、まったく同じタイミングで心まで大人になり、自分の将来に関わる大きな決断を迷いなく行える人は非常に少ないです。
モラトリアムは、そんな青年期の若者が、多様な経験を通じ、「自分がどのような人間なのか」「将来どのようになっていたいか」などを模索するための時期なのです。
モラトリアムは、青年期の人間たちが、自身のアイデンティティを確立するまでに必要な期間です。
精神分析学者のエリクソンの定義から考えると、青年期は13歳~19歳の年齢に当たります。
この定義と、実際に社会に出る直前であり、自分の将来や自分自身について考える時期だという点を合わせて、高校生から大学生の間がモラトリアムと表現されることが多いです。
「モラトリアム」の種類
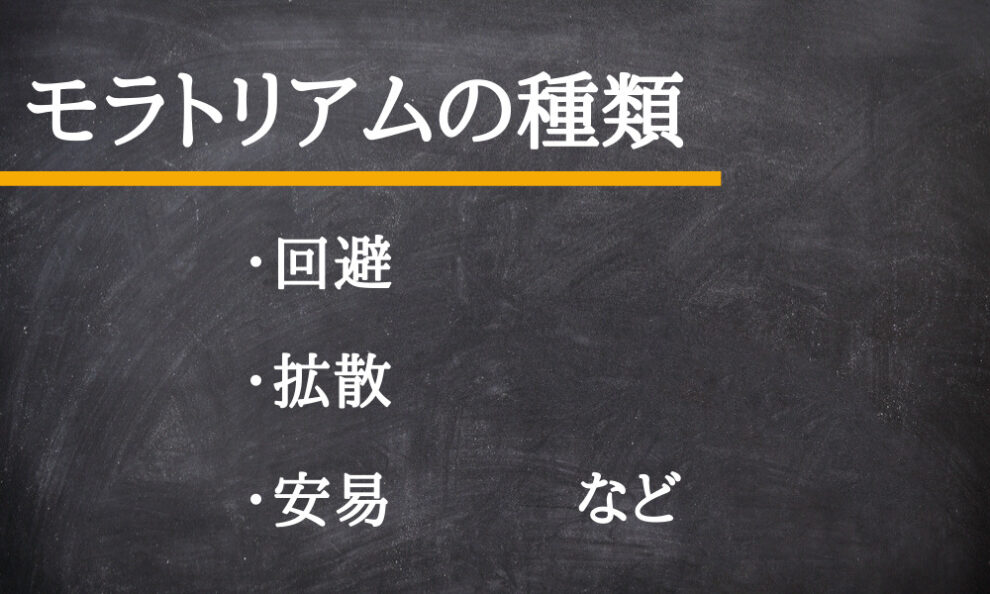
モラトリアムは、以下のような5つの状態に分けられます。
どのようなモラトリアム期を迎えるかは人それぞれ異なります。
- 回避
- 拡散
- 安易
- 延期
- 模索
それぞれの状態を詳しく見ていきましょう。
要素➀:回避
モラトリアム期間には、社会進出に向けての準備が求められることが多いです。
将来どのような仕事に就くか、どのような人間になりたいかなどの人生設計をする必要があります。
回避とは、そのような将来のことから完全に目をそらした状態となります。
要素➁:拡散
拡散とは、自分の将来のことを考えてはいるものの、さまざまな選択肢にあれこれと目移りしすぎて方向性が定まらないことです。
現実味のない選択肢や、少しでも気になること全てを選択肢に入れて動いてしまうため、進むべき道を見つけられない状態です。
要素➂:安易
安易とは、自分の頭で考えず、人の意見に引っ張られてしまっている状況です。
周りから誘われるままに気軽に行動をしますが、自身の将来について考えているわけではありません。
ただし、このような気軽な行動が結果的に将来に影響を与える場合もあるので、必ずしもこの状態が悪いこととは言えません。
要素➃:延期
延期とは、現状がモラトリアム期間であるということを理解したうえで、社会的責任から逃れて自分の思うままに時間を過ごしている状態です。
自分で決めた期間やを過ぎたり、必要に迫られたりした場合には社会の一員として動くことができるのが特徴です。
要素➄:模索
模索とは、具体的に職業や将来設計などを検討している状態です。
自身について考え、アイデンティティを確立したうえで、自分が就きたい職業や、続けられるであろう職業を探すことができるのです。
「モラトリアム」の経済における意味
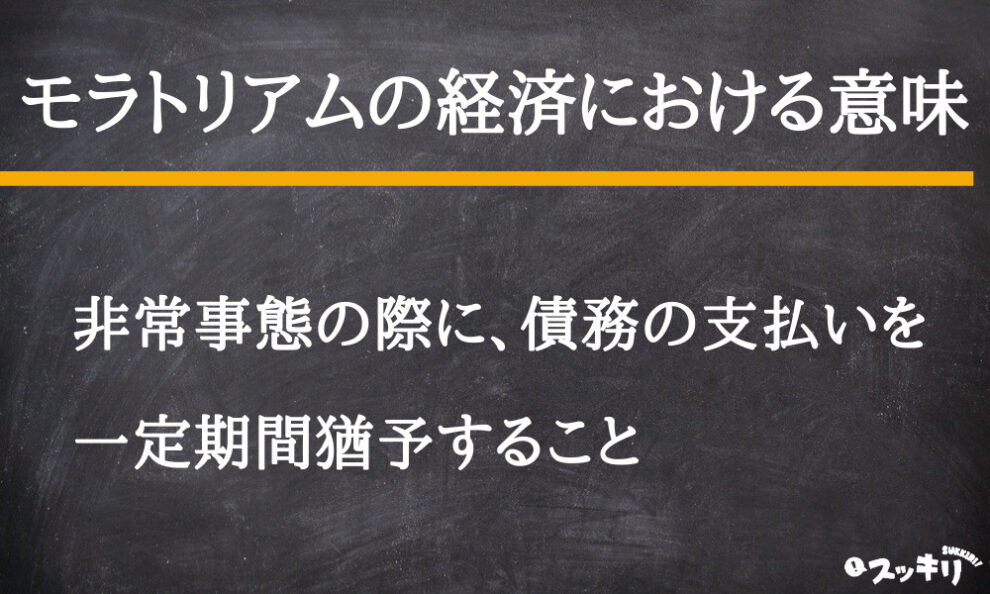
経済におけるモラトリアムの意味は、天災・恐慌・戦争などの非常事態の際に、債務の支払いを一定期間猶予することです。
このように、金融業界で使われる意味のモラトリアムは特に、「金融モラトリアム」と言うこともあります。
不景気などで融資の返済が難しい人に対し、支払いを猶予することを金融モラトリアムと言います。
実際に日本でも、1923年の関東大震災の直後や、1927年の金融恐慌後にモラトリアムを実施しています。
もともとは、このような経済用語として使われていたモラトリアムが、心理学用語としても使われるようになったのです。
モラトリアムには、心理学における意味や、経済における「債務の支払いの猶予」という意味以外にも「製造・使用・実施などの一時停止」という広い意味があります。
この意味のモラトリアムは、主に核実験や戦争、死刑執行に関して使われることが多いです。
「モラトリアム」の使い方
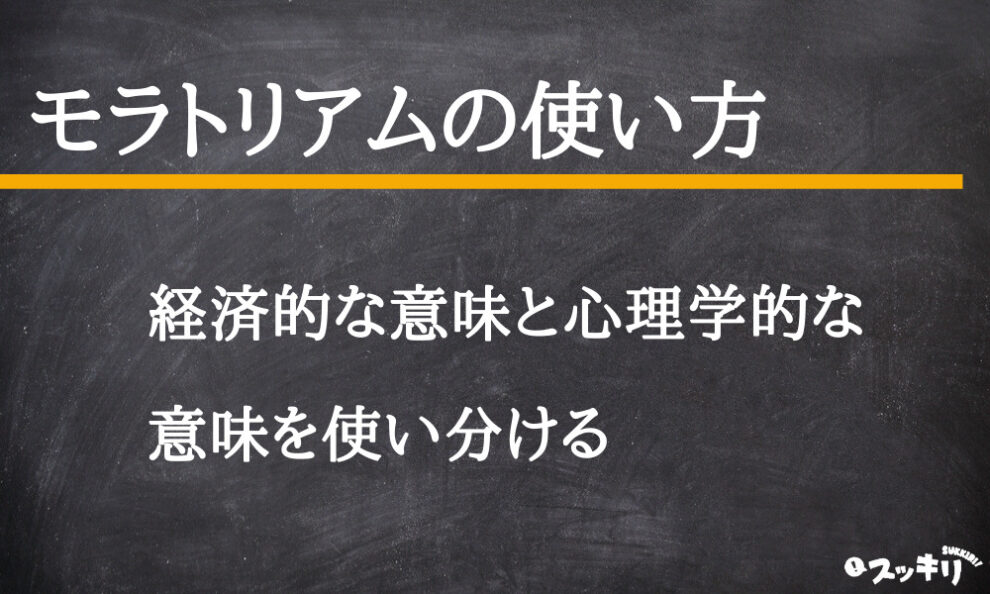
モラトリアムは、主に心理学的な意味と経済的な意味で使われます。
どちらの意味で使われているのかは、文脈から判断する必要があります。
また、モラトリアムは以下のような形で使われることが多いです。
- モラトリアムを〇〇する
- モラトリアム〇〇
- 〇〇モラトリアム
具体的には、モラトリアムを採択する、モラトリアムを宣言するなどの表現が使われることがあります。
実際に、モラトリアムを使った例文を見ていきましょう。
- もう少しモラトリアム期間が欲しいね。
- 正直に言うと、モラトリアムを伸ばすために大学進学を決めた。
- モラトリアムによって救済された企業がたくさんある。
➀と➁のモラトリアムは「社会的責任・義務が猶予されている青年の時期」という意味で使われています。
➂のモラトリアムは、「天災・恐慌・戦争などの非常事態の際に、債務の支払いを一定期間猶予すること」という意味で使われています。
「モラトリアム」の語源
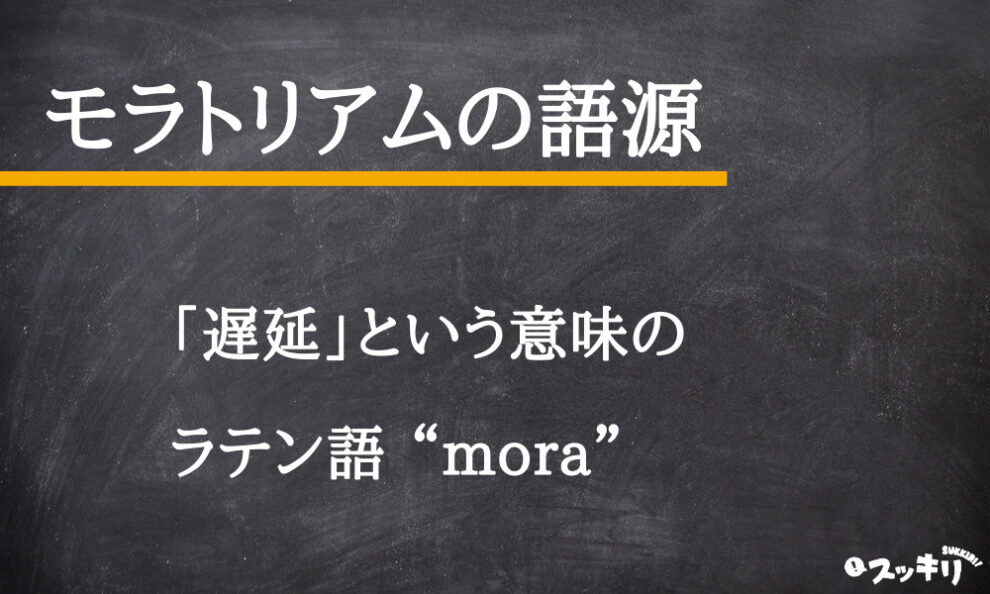
「モラトリアム」の語源は「遅延」という意味のラテン語 “mora” です。
これが「遅延する」という意味のラテン語 “morari” に派生しました。
ここから、英単語 “moratorium” が生まれ、これをカタカナ語表記したのがモラトリアムです。
ちなみに、モラトリアムはモラルという言葉とは無関係です。
同じ語源と勘違いされることも多いのですが、語源も異なります。
「モラトリアム」の類義語
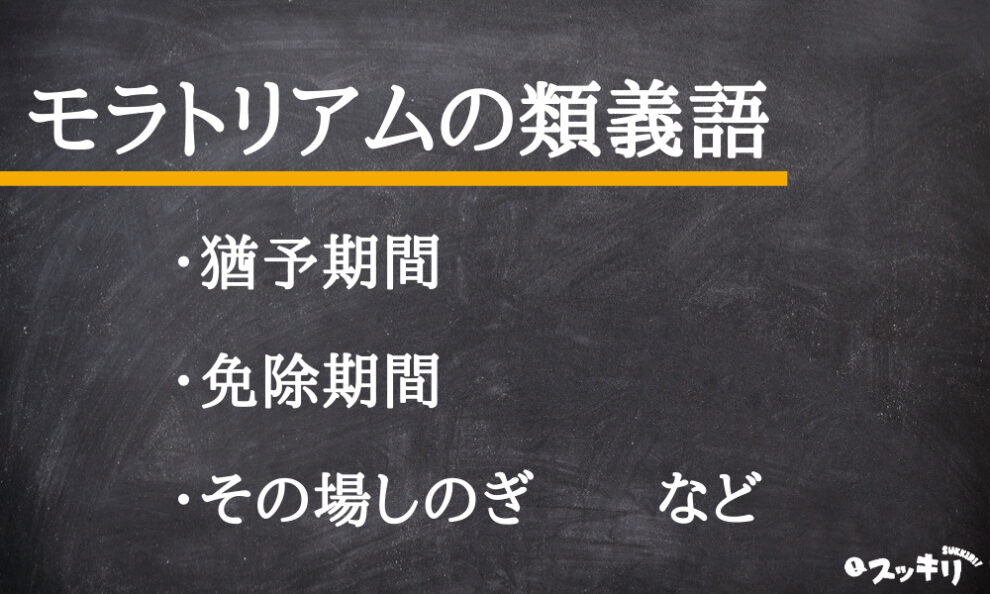
モラトリアムには以下のような類義語があります。
- 猶予期間
引き延ばして、決定・実行しない期間 - 免除期間
負うべき義務の負担が免じられている期間 - その場しのぎ
その場、その一瞬を取りつくろう為の一時的な対応 - 場当たり的
その場、その一瞬を取りつくろう為の一時的な対応 - ギャップイヤー
大学卒業後の1年~数年間、就職をせず自主的に空けてる期間
「モラトリアム」の関連語
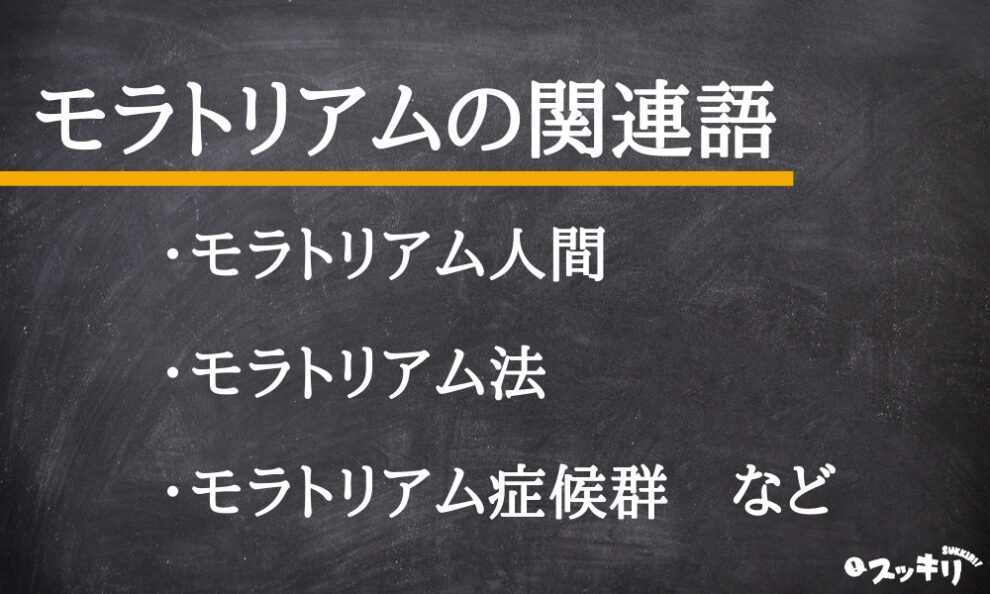
モラトリアムの関連語には以下のようなものがあります。
- モラトリアム人間
社会人としての当事者意識がなく、大人社会に適応できない人間 - モラトリアム法
リーマンショックで経営が悪化した中小企業への臨時処置を定めた法律 - モラトリアム症候群
社会に出て大人として振る舞うことに対して抵抗を覚える状態 - ベトナムモラトリアム
アメリカ空軍による北ベトナム本土への直接的空爆の停止を要求したデモ活動 - フーバー・モラトリアム
アメリカが行った第一次世界大戦による債務の支払いを1年間猶予する措置
「モラトリアム人間」の意味
モラトリアム人間とは、大人にならなければいけない時期なのにも関わらず、大人になることを拒否している人間のことです。
「大人になることを拒否している」とは、「大人になるための心理的葛藤や人生の選択、社会的責任を拒否し、逃げ続けている状態」を表します。
また、すでに社会人なのにもかかわらず社会人としての当事者意識がなく、大人社会に適応できない人間を指すこともあります。
簡単に言えば、大人になろうとしない人や「大人になりたくない」と思っている人のことを表すのです。
モラトリアム人間とは、精神科医の小此木啓吾(おこのぎけいご)が、現代の若者の気質を表す言葉として提唱した概念です。
1978年に出版された小此木啓吾の著書『モラトリアム人間の時代』でモラトリアムという言葉が日本で広く知られました。
具体的に例を挙げれば、大学を卒業してもやりたいことが定まらず、親に金銭的に依存しながら自分の好きなことだけをして生きている若者がモラトリアム人間になります。
1970年代にモラトリアム人間にあたる若者が多く出てきた理由としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 急激な社会の変化
- 高学歴化
- 経済的余裕
それぞれの要因について詳しく解説します。
理由➀:急激な社会の変化
1970年代は、高度経済成長によって急激な社会の変化が起こった時代でした。
これにより、社会構造や将来の選択肢が多様化、複雑化することで、それを選びとるのが難しくなっていたのです。
理由➁:高学歴化
また、この時代は大学進学率が伸びており、社会全体が高学歴化していました。
それに伴って、大企業や人気企業に就職するためには、高い学歴が求められるようになりました。
そのため、昔よりも若者の勉強必要が長くなり、結果として自分自身を見つめなおす時間がなくなってしまったのです。
以前ならば若者が獲得していた、自由に過ごしながら自身を見つめ直す期間が勉強によって奪われてしまうことでモラトリアムが遅れるようになったのです。
理由➂:経済的余裕
この時代、日本の暮らしは高度経済成長により生活が豊かになっており、多くの過程が経済的余裕を獲得していました。
そのため、生き抜くために、高校卒業してすぐなどのタイミングで無理やり働く必要性が弱まっていたのです。
ちなみに、モラトリアム人間には以下のような類義語・関連語があります。
- ピーターパン症候群(Peter Pan Syndrome)
年齢的には大人だが、精神的に成熟していない男性 - パラサイト・シングル(Parasite single)
社会人になってからも、基本的な生活面で親に依存する未婚者
「モラトリアム法」の意味
モラトリアム法とは、リーマンショックで経営が悪化した中小企業や個人を救済するために2009年12月に制定された法律です。
中小企業や個人が債務返済の猶予や軽減を求めた場合、金融機関にそれに応じるよう努めるよう命じる内容です。
このモラトリアム法のモラトリアムは、「天災・恐慌・戦争などの非常事態の際に、債務の支払いを一定期間猶予すること」という意味で使われています。
モラトリアム法の正式名称は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」です。
多くの場合は略して「中小企業円滑化法」と呼ばれます。
「モラトリアム症候群」の意味
モラトリアム症候群とは、社会に出て大人として振る舞うことに対して抵抗を覚える状態、症状を指します。
「ピーターパン症候群」と同じ意味の言葉です。
「ベトナムモラトリアム」の意味
ベトナムモラトリアムとは、ベトナム戦争停戦というアメリカ空軍による北ベトナム本土への直接的空爆の停止を要求したデモ活動です。
このデモ活動には学生が多く参加したため、心理学用語としてのモラトリアムの意味だととらえられてしまうことが多いです。
しかし、このモラトリアムは、「使用・実施などの一時停止」という意味で使われています。
「フーバー・モラトリアム」の意味
フーバー・モラトリアムとは、アメリカのフーバー大統領がヨーロッパ諸国に対して行った、第一次世界大戦による債務の支払いを1年間猶予する措置のことです。
「モラトリアム」のまとめ
以上、この記事ではモラトリアムについて解説しました。
| 英語表記 | モラトリアム(moratorium) |
|---|---|
| 意味 | 社会的責任や義務が猶予されている青年の時期 |
| 語源 | 「遅延」という意味のラテン語 “mora” |
| 類義語 | 猶予期間 免除期間など |
モラトリアムは心理学用語なので少し難しいと感じてしまう人もいるかもしれませんが、この機会にしっかりと理解しておきましょう。