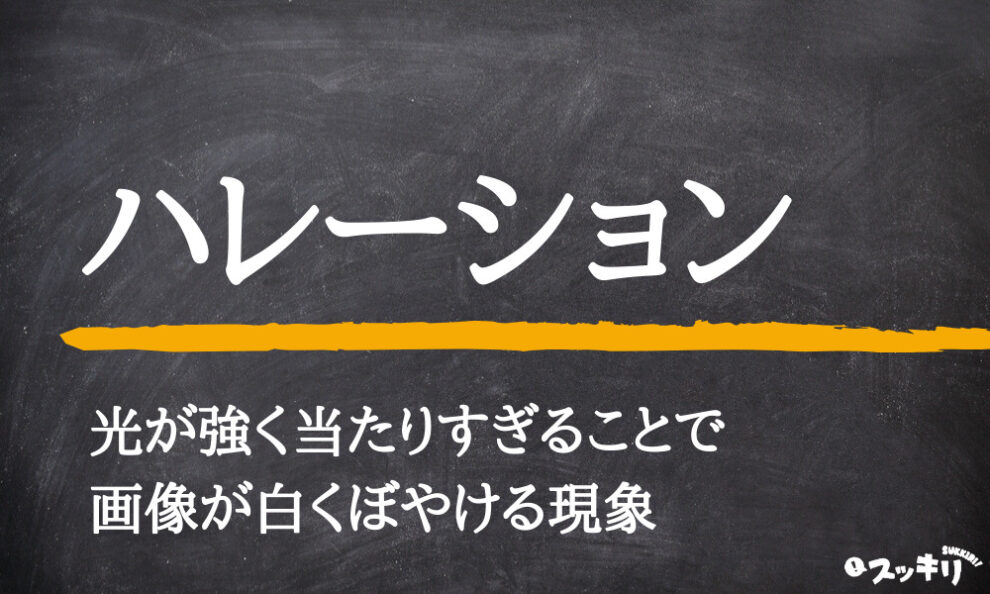ハレーションとは「光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象」という意味です。
医療やビジネスなどさまざまな場面で使われる言葉ですが、専門的な用語なので意味を知らない人も多いでしょう。
この記事では、分野ごとの意味を詳しく解説します。
☆「ハレーション」をざっくり言うと……
| 英語表記 | ハレーション(halation) |
|---|---|
| 意味 | 光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象 |
| 語源 | 「強い光が当たった部分の白いぼやけ」という意味の英単語 “halation” |
| 類義語 | 光暈 光滲など |
| 対義語 | 好影響 好都合など |
このページの目次
「ハレーション」の意味
光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象
例:昨日の写真はハレーションが起きていた。
ハレーションは、カメラで写真を撮った際に、光が強く当たりすぎることでその周辺が白くぼやけたり濁ったりしてしまう現象を表す言葉です。
ハレーションはフィルムカメラなどの銀塩写真で起こる現象であり、デジタル写真で起こることはありません。
「ハレーション」が起こる仕組み
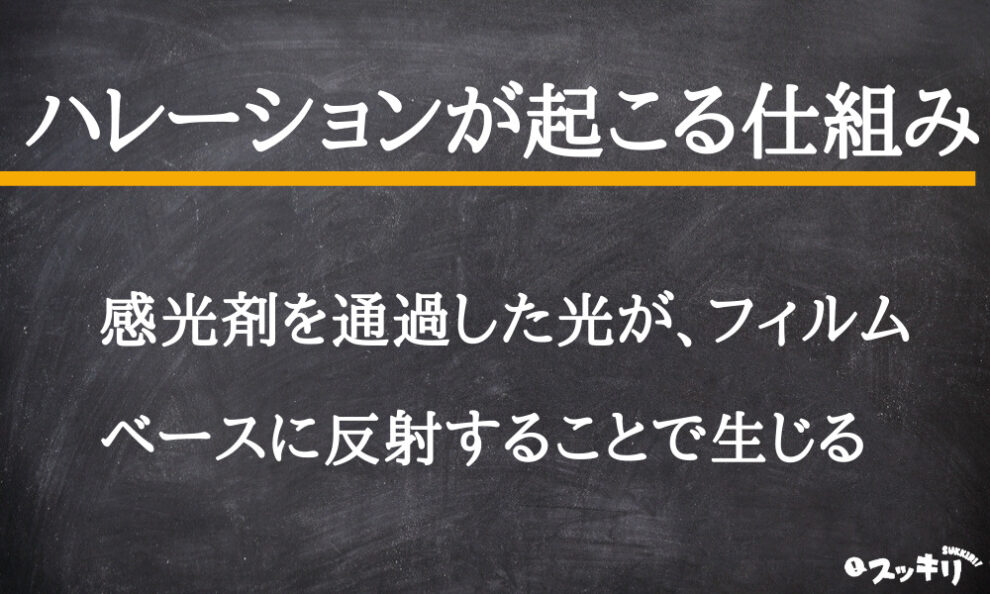
フィルムは合成樹脂のフィルムベース(支持体)の上に、光によって変化する感光剤というものが塗布されています。
感光剤は光によって変化するので、レンズを通して入った風景は感光剤の層に映し出されます。
しかし光が強すぎると、感光剤を通過した光が、さらに下のフィルムベースに反射して再び感光剤に戻ってきてしまうことがあります。
これがハレーションが起こる仕組みです。
「ハレーション」の分野ごとの意味
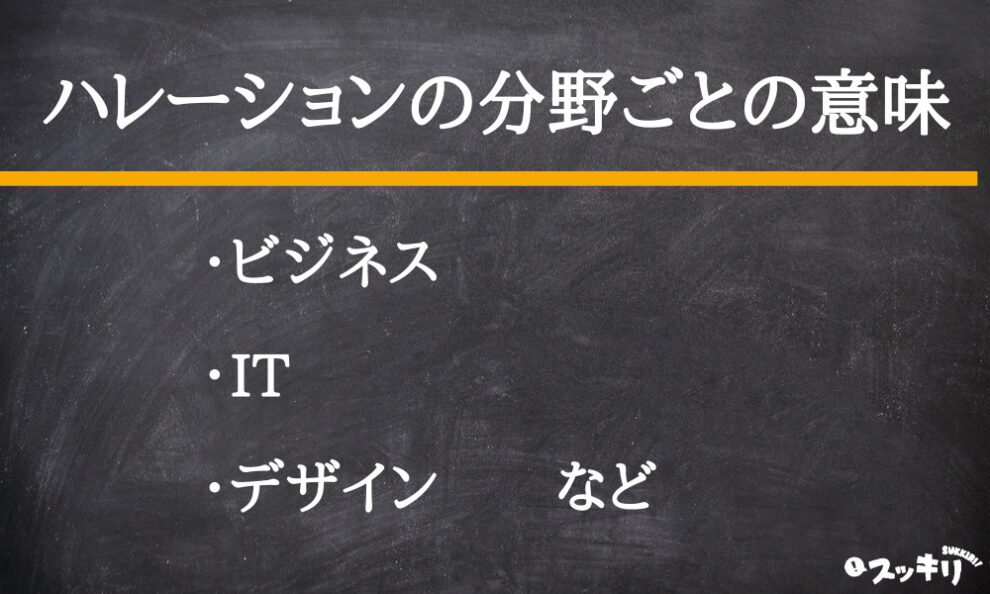
ハレーションは、上記のカメラでの意味から派生して、以下のような分野でも使われるようになりました。
- ビジネス
- IT
- デザイン
- 医療
- アート
- 美容院
それぞれの分野ごとの意味を詳しく解説します。
分野➀:ビジネス
ビジネスの場で広く使われるハレーションの意味は、「周囲に悪い影響を及ぼすこと」です。
人や行為が、周りに悪い影響を与えることを広く表す言葉です。
悪い影響に限定せず「影響を強く及ぼすこと」という意味で使われることもあります。
しかし、基本的には「悪い影響」という意味で使われるので、覚えておきましょう。
分野➁:IT
ITの分野におけるハレーションは「ひとつの操作や作業のミスが全体に大きな悪影響を及ぼすこと」という意味です。
ビジネス用語のハレーションは、「人が周囲に悪い影響を与えること」という意味も含みますが、ITではそのような意味はありません。
分野➂:デザイン
デザイン分野におけるハレーションは、「明るい色同士の組み合わせ」のことです。
ハッキリとした黄色や赤色、白色など、彩度が高い色が多く使われていて、目がチカチカするような色使いのことを表します。
ハレーションは派手な見た目で、人の目を引き付けやすいですが、使い過ぎるとデザイン自体が見づらくなってしまうので注意が必要です。
分野➃:医療
医療の分野でのハレーションは、CTやMRIで光が反射してしまい画像が写らない現象のことです。
CTとは放射線を利用して物体の内部を画像化する技術で、MRIとは磁石と電磁波を用いて物体の内部を画像化する技術のことです。
これらの医療の装置では、金属の周囲が光が反射して白くなり、画像が写りません。
そのため、腕時計やアクセサリーは外しますが、歯列矯正の器具や骨折を治療などのために体内に入っているボルトの周りではハレーションが起きてしまいます。
分野➄:アート
アートにおけるハレーションは、「風景の光の表現」もしくは「作品内の人物の神々しさや、眩しさの表現」です。
例えば、以下のクロード・モネの『パラソルを指す女』では、背景の明るさが非常に印象的な絵です。

空が眩しいようすが伝わり、思わず目を細めて見てしまいそうになりますよね。
このような、芸術作品に使われる光の表現をハレーションと言います。
分野➅:美容院
美容院におけるハレーションとは、「施術後に髪の毛がチリチリになってしまう現象」のことです。
縮毛矯正やデジタルパーマなどの施術をした際に、髪へのダメージが大きすぎると髪の毛がチリチリになってしまうことがあります。
ハレーションが起きてしまったら直すことはできないので、髪が伸びるのを待ってカットするしかありません。
「ハレーション」の使い方
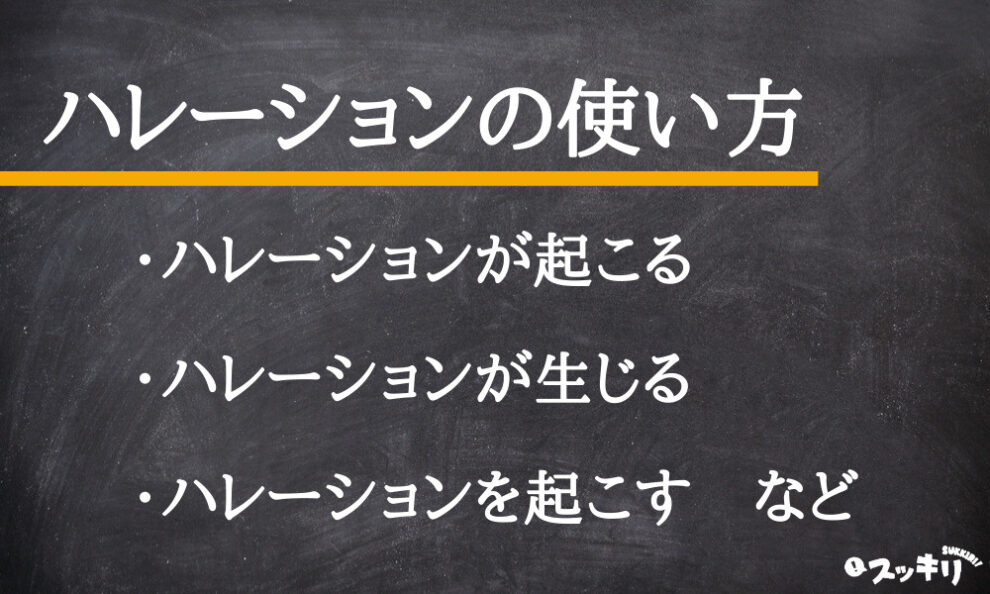
ハレーションは、以下のような使い方をします。
- ハレーションが起こる
- ハレーションが生じる
- ハレーションを起こす
- ハレーションを引き起こす
- ハレーションが大きい・小さい
これらを踏まえて具体的な例文を見ていきましょう。
- この写真はハレーションが起こっていて使い物にならない。
- 僕のせいでプロジェクトにハレーションが生じているので残業確定だ。
- 新しいロゴはハレーションを活用して目立つようにしている。
- 矯正器具がハレーションを引き起こしています。
➀のハレーションは、「写真で光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象」という意味で使われています。
➁のハレーションは、「ビジネスシーンで周囲に悪い影響を及ぼすこと」という意味で使われています。
➂のハレーションは、「周囲に悪い影響を及ぼすこと」という意味で使われています。
➃のハレーションは、「CTやMRIで光が反射してしまい画像が写らない現象」という意味で使われています。
「ハレーション」の語源
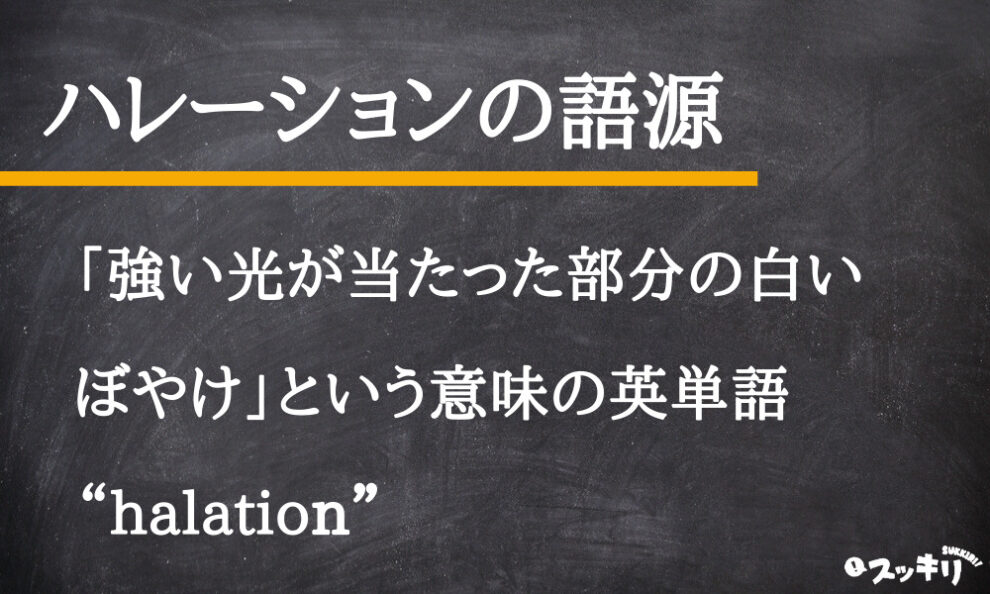
ハレーションの語源は「強い光が当たった部分の白いぼやけ」という意味の英単語 “halation” です。
ビジネスやITでの「悪い影響を与えること」という意味は、カタカナ語のハレーション限定の意味なので注意しましょう。
「悪い影響」を英語で表現したい時には “bad influence” などの表現を用いると良いでしょう。
「ハレーション」に似た現象
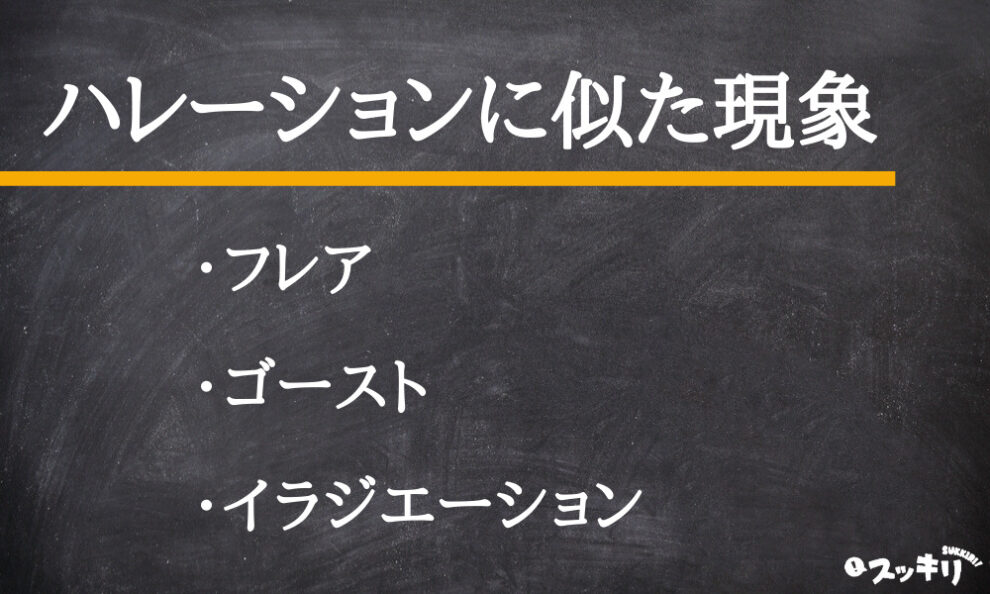
「光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象」という意味のハレーションには、以下のような似た現象があります。
- フレア
- ゴースト
- イラジエーション
それぞれの現象と、ハレーションの違いを詳しく解説します。
現象➀:フレア
フレアとは、「レンズの中に強い光が入ることで、カメラ内部で反射して画面が白くぼやけること」という意味です。
下の画像のように、太陽やスポットライトなどの強い光源が、直接もしくはそれに近い形でレンズに当たった場合に、光源の周辺や画面全体を白っぽくして写真がぼやけてしまいます。

起こる結果自体は非常に似ていますが、ハレーションとフレアには以下のような違いがあるのです。
- ハレーション
フィルムベースで反射した光で再び感光層が感光すること - フレア
強い光が直接入ることでレンズやカメラボディ内部で反射されて起こる
つまり、ハレーションとフレアは起こる原因が全く異なります。
ハレーションはフィルムカメラでしか起こりませんが、フレアはデジタルカメラでも起こる現象です。
フレアは「レンズフレア」と言われることもあります。
現象➁:ゴースト
ゴーストとは、レンズの中に強い光が入り、カメラ内部で反射して光の玉が写ってしまう現象です。
以下の写真でも、太陽の周りに光の玉がいくつも映っていますね。

ゴーストは、以下の2点がハレーションと異なります。
- 強い光が直接入ることでレンズやカメラボディ内部で反射されて起こる点
- 本来は存在しない光の玉が映るという点
つまり、現象そのものも、その原因も、ハレーションとは異なるのです。
現象➂:イラジエーション
イラジエーションとは、「フィルムに強い光が当たって写真の周りが黒くなって不鮮明になってしまうこと」です。
ハレーションと同じように、フィルムカメラで起こる現象で、原因は同じです。
しかし、ハレーションとイラジエーションには以下のような違いがあります。
- ハレーション
画像が白くぼやける - イラジエーション
画像の周囲が黒くなる
つまり、上記の2つは、起こる現象自体が異なるのです。
「ハレーション」の類義語
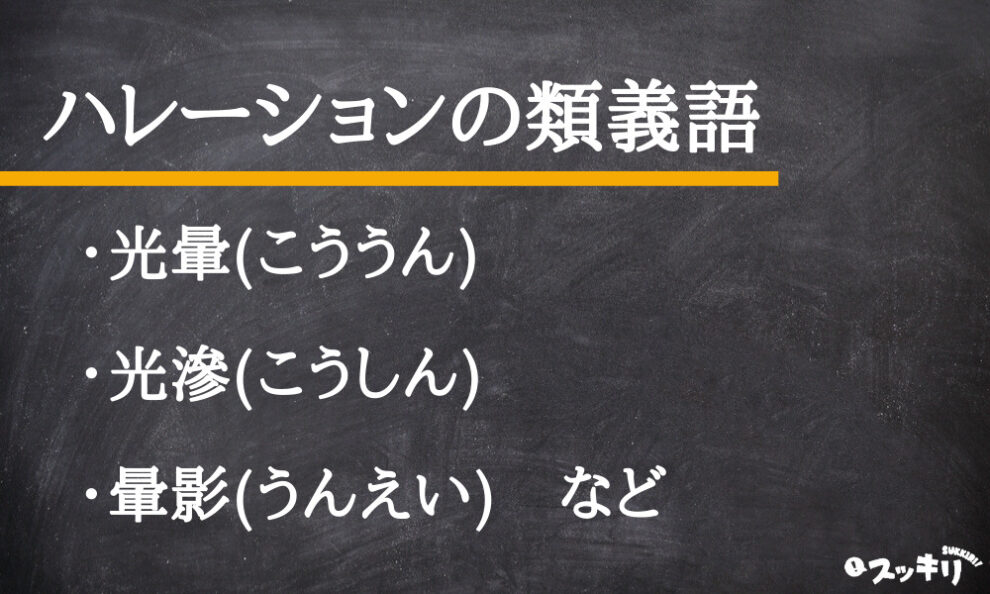
ハレーションには以下のような類義語があります。
- 光暈(こううん)
強い光の周辺にできる淡い光の輪 - 光滲(こうしん)
強い光によって画像が不鮮明になること - 暈影(うんえい)
強い光で画像が白くにじむこと
- 悪影響
良くない影響のこと - 副作用
目的とする作用に伴って起こる別の作用のこと - 逆効果
期待とは逆の結果が出ること
「ハレーション」の対義語
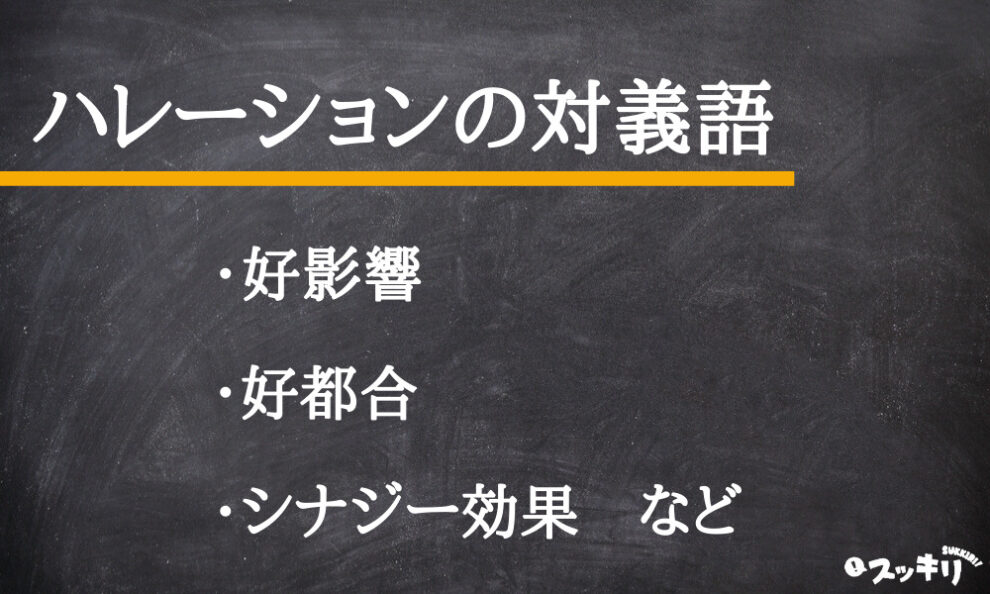
ハレーションには以下のような対義語があります。
- 好影響
好ましい影響のこと - 好都合
都合が良いこと - シナジー効果
ある要素とある要素が組み合わされることによって単体以上の結果が得られること - プラス効果
良い効果のこと
どれも、ビジネスの分野で使われるハレーションの対義語です。
「ハレーション」への防止策
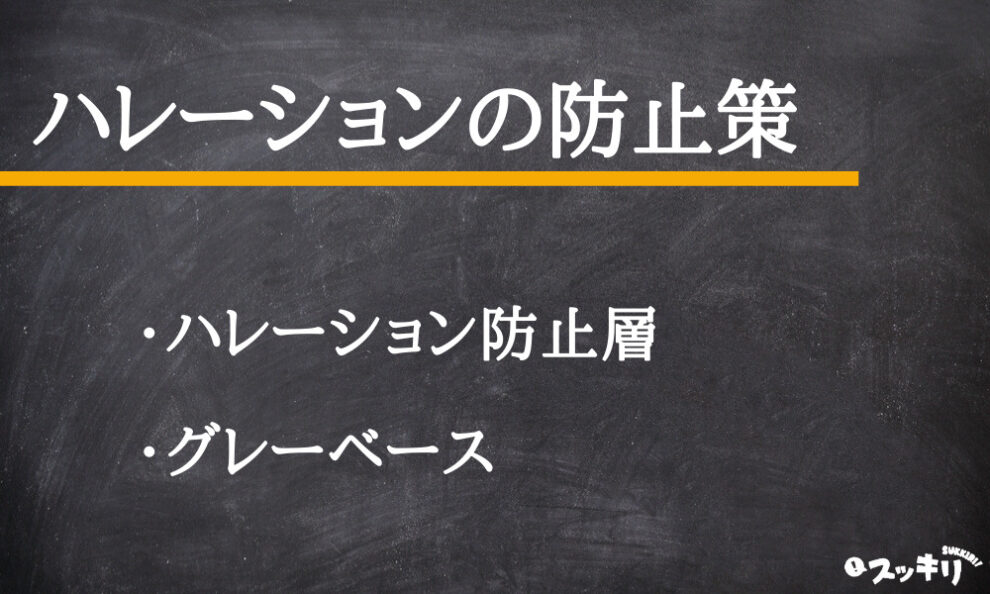
ハレーションを起こさないための対策として、以下のような方法が取られています。
- ハレーション防止層
フィルムベースに染料を塗布する - グレーベース
フィルムベース自体を薄く着色させて反射光を弱くする
「ハレーション」のまとめ
以上、この記事ではハレーションについて解説しました。
| 英語表記 | ハレーション(halation) |
|---|---|
| 意味 | 光が強く当たりすぎることで画像が白くぼやける現象 |
| 語源 | 「強い光が当たった部分の白いぼやけ」という意味の英単語 “halation” |
| 類義語 | 光暈 光滲など |
| 対義語 | 好影響 好都合など |
カメラの仕組みは専門的な内容なので理解が難しい部分もありますが、言葉は使いこなせるようにしておきましょう。