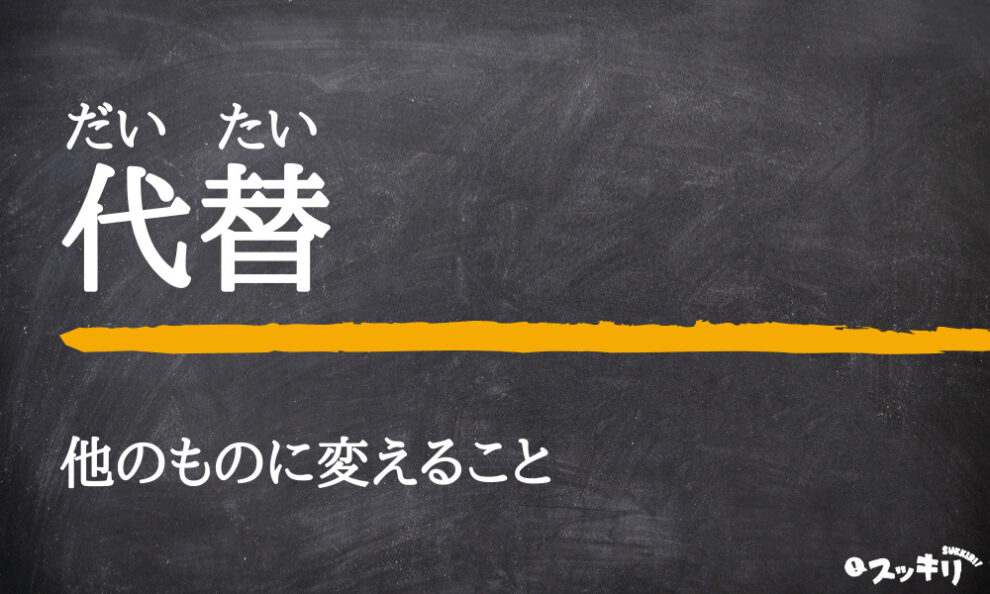代替は「他のものに変えること」という意味です。
代替は「代替案」「代替品」などの形でビジネスシーンでもよく使われる言葉です。
しっかりと意味や使い方をマスターしておきたいですよね。
そこで、この記事では代替の意味から使い方まで詳しく解説しています。
☆「代替」をざっくり言うと……
| 読み方 | 代替(だいたい) |
|---|---|
| 意味 | 他のものに代えること |
| 語源 | 「代」も「替」も「かえる」の意味 |
| 類義語 | 交換 代理 交代 など |
| 英語訳 | substitute(代わりに) alternative(代わりになる) replace(取って代わる) |
「代替」の意味
他のものに変えること
代替はあるものに不都合などが発生した時に、同じ用途を果たせる別のもので代用することを表します。
たとえば、スマホを修理に出した時には、修理期間中に不便でないよう、代替となるスマホを貸し出してくれる会社が多いです。
代替となるものは必ずしも同じものである必要はありません。同じ用途を果たせるものであれば別のもので代用しても良いのです。
たとえば、料理ではバターをマーガリンで代用できる場合が多いです。
「代替」の読み方
代替はだいたいと読みます。
また、本来は正しい読み方ではありませんが、だいがえと呼ばれる場合があります。
そして、「だいがえ」と呼ばれる場合には「代替え」という表記が用いられることがあります。
「代替」の使い方
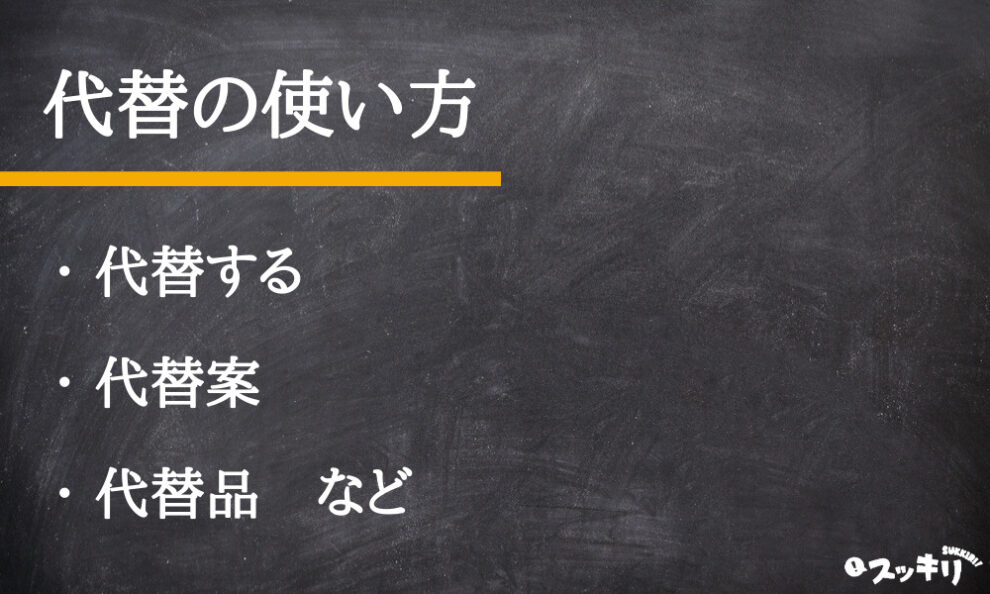
代替はある物事Aをある物事Bで代用する時に用いられます。
AとBは同じもののこともありますが、違うものの場合もあります。
代替は以下のような表現で用いられることが多いです。
- 代替する
- 代替案
- 代替品
- 代替地
- 代替刑
- 代替財
- 代替機
それぞれの表現について例文と一緒に詳しく見ていきましょう。
代替する:あるものをあるものの代わりに用いる
「代替する」とは、あるものをあるものの代わりに用いるという意味です。
「AでBを代替する」という形で用いることが多いです。
- 時間がなくなってしまったので、タクシーでの移動で徒歩を代替する。
代替案:ある案の代わりになる案
代替案とは、ある案の代わりになる案のことです。
A案が何らかの事情で使えなくなってしまった場合に使われる案のことを指します。
- 提案が却下された時に備えて代替案を準備しておくように。
代替品:あるモノの代わりになるモノ
代替品とは、あるモノの代わりになるモノのことです。
代替品は、いつも使っているスマホの代わりとなる別のスマホなど、同じ製品の場合もありますが、バターの代わりのマーガリンなど、別の製品の場合もあります。
- バターの代替品としてマーガリンを使用する。
代替地:ある土地の代わりになる土地
代替地とは、ある土地の代わりになる土地のことです。
公共事業を行うために土地を買収した時に、代わりに提供される土地のことを指します。
通常は土地を買収する費用を金銭で支払いますが、土地所有者の要求によっては代替地を用意することがあります。
たとえば、ダムを建設するために土地を買収する時には替わりの土地を提供する場合があります。
- ダム建設で住居を追われた人に代替地が提供される。
代替刑:受刑者を刑務所に収容しない代わりに社会奉仕をさせること
代替刑とは、受刑者を刑務所に収容しない代わりに、社会奉仕活動に参加させることです。
死刑が廃止された時に、死刑の替わりになる刑罰のことを指す場合もあります。
- 死刑の代替刑に何が適切か、議論が交わされている。
代替財:ある製品やサービスと同じニーズを満たす製品・サービス
代替財とは、ある製品やサービスと同じニーズを満たす製品やサービスのことです。
たとえば、飛行機は遠くに早く行きたいという新幹線と同じニーズを満たすサービスと言えます。
- 技術革新により、スマホの代替財が出現するか注目が集まっている。
代替機:修理中の機械の代わりに貸与される機械
代替機とは、修理中の機械の代わりに貸与される機械のことです。
たとえば、パソコンは修理に出すと、修理中に使う用に別のパソコンが貸与される場合があります。
- 故障で修理に出したのに、代替機まで故障して困惑している。
「代替」の語源
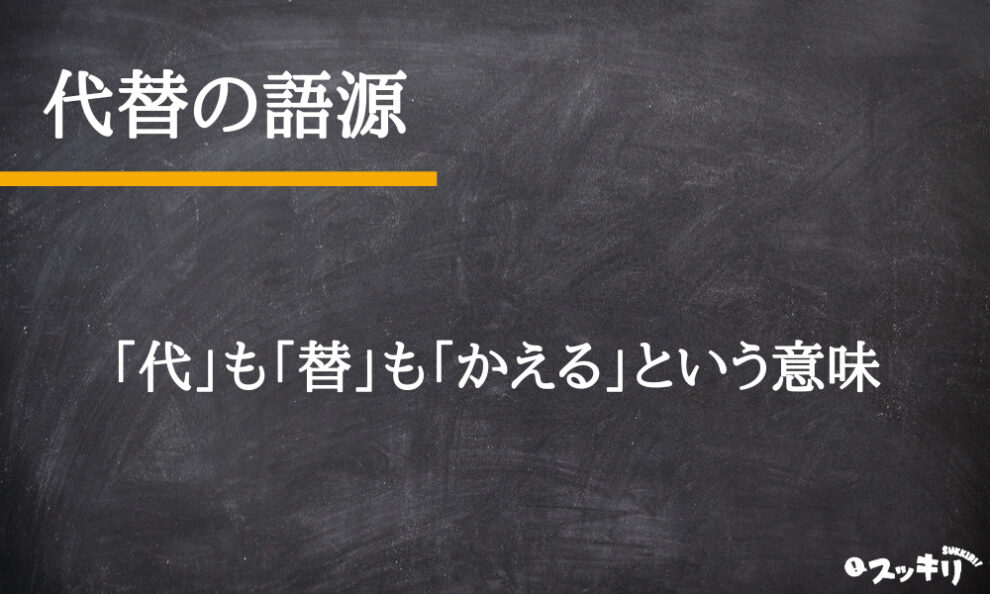
代替を構成する漢字には以下のような意味があります。
- 代
あるものを取り除いて、他のものを入れること - 替
あるものを取り替えること
代替は何かをかえることを表す漢字2つを組み合わせて、「何かを何かにかえる」という意味を持つようになりました。
「代替」の類義語

代替には以下のような類義語があります。
- 交換(こうかん)
物と物を取り換えること - 代理(だいり)
その人に代わって物事を処理すること - 交代(こうたい)
人が入れ替わって役割を引き継ぐこと - 置換(ちかん)
あるものとあるものを置き換えること - 代行(だいこう)
ある人に代わって物事を行うこと - 代用(だいよう)
何かを何かの代わりに用いること - 替え玉(かえだま)
本人だと偽って別人を使うこと - 振替(ふりかえ)
一時的に他のものを代わりに用いること
「交換」の意味:物と物を取り換えること
交換とは、物と物を取り換えることという意味です。
相手のものと自分のものを入れ替える時に用います。
たとえば、名刺交換では自分の名刺を相手に渡し、相手の名刺をもらいます。
- クリスマスパーティーでプレゼント交換を行った。
「代理」の意味:その人に代わって物事を処理すること
代理とは、その人に代わって物事を処理することです。
たとえば、何らかの事情で店長が業務を行えない時には、代理店長が店長の業務を行います。
- 休職中の担当者の代理として、若い女性が来た。
「交代」の意味:人と人が入れ替わって役割を引き継ぐこと
交代とは、人と人が入れ替わって役割を引き継ぐことです。
- サッカーで選手交代が行われる。
「置換」の意味:あるものとあるものを置き換えること
置換とは、あるものとあるものを置き換えることです。
科学の分野である物質をある物質で置き換える時に用いられたり、IT分野である文字や画像などを他のものに置き換える時に使われたりします。
- 会社名が変わったので、旧社名を新社名に置換する。
「代行」の意味:ある人に代わって物事を行うこと
代行とは、ある人に代わって物事を行うことです。
誰かが誰かの代わりになる場合に用いられることが多いです。
- 退職代行サービスが話題だ。
「代用」の意味:何かを何かの代わりに用いること
代用とは、何かを何かの代わりに用いることです。
代替と意味が似ていますが、以下のような違いがあります。
- 代替
代えた後に元に戻さない - 代用
代えた後に元に戻す
代替と代用では、代えた後に元に戻すかどうかが異なるのです。
- のりをご飯粒で代用する。
「替え玉」の意味:本人だと偽って別人を使うこと
替え玉とは、本人だと偽って別人を使うことです。
また、ラーメンで残したスープにおかわりとして入れる麺のことを指す場合もあります。
- 替え玉受験を指摘され不合格になった。
- ラーメン屋で替え玉を頼む。
「振替」の意味:一時的に他のものを代わりに用いること
振替とは一時的に他のものを代わりに用いることです。
銀行などである口座から同じ銀行の同じ支店の口座に資金を移動させる行為を指すこともあります。
- 普通預金から定期預金に振替を行った。
「代替」の英語訳

代替を英語に訳すと、次のような表現になります。
- substitute
(代わりに)
例:I will substitute fruits with tomatoes.
(フルーツの代わりにトマトを使う。)
- alternative
(代わりになる)
例:alternative energy sources
(代替となるエネルギー源) - replace
(取って代わる)
例:Develop devices that can replace smartphones.
(スマホの代わりになるデバイスを開発する。)
「代替」のまとめ
以上、この記事では代替について解説しました。
| 読み方 | 代替(だいたい) |
|---|---|
| 意味 | 他のものに代えること |
| 語源 | 「代」も「替」も「かえる」の意味 |
| 類義語 | 交換 代理 交代 など |
| 英語訳 | substitute(代わりに) alternative(代わりになる) replace(取って代わる) |
代替は日常生活の中でも使用頻度が多い単語になっています。
間違えないように使っていきたいですね。